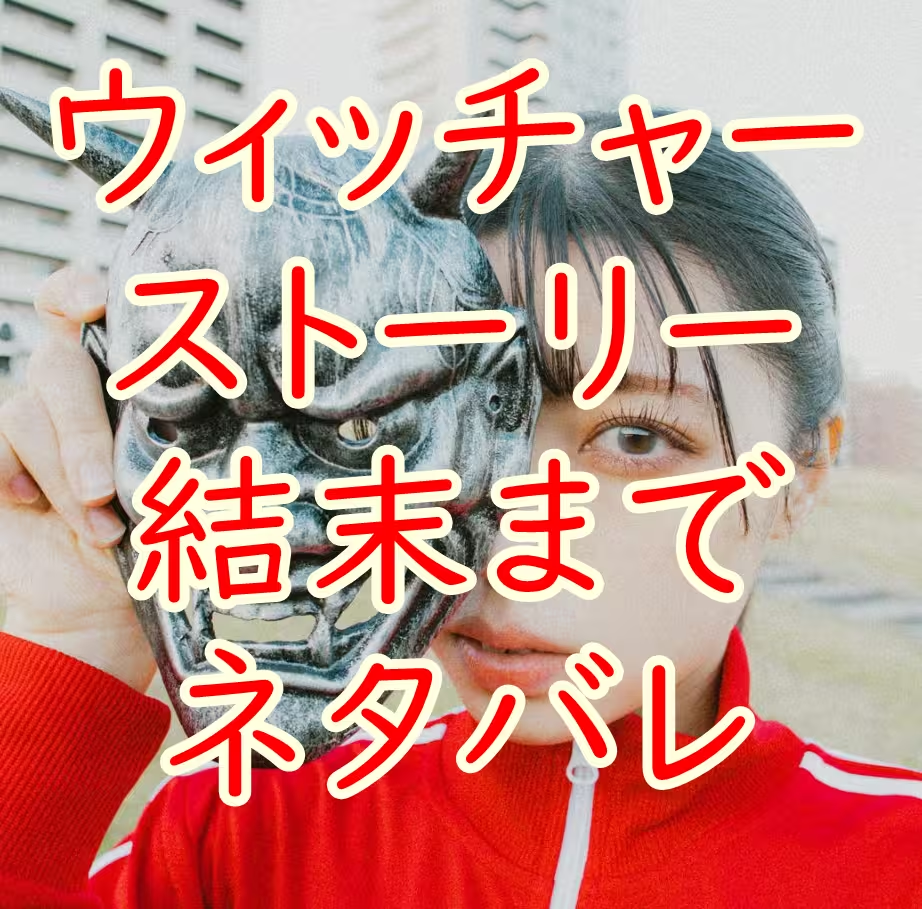深呼吸をひとつ。高いところから壮大な世界を見渡すように、まずは『ウィッチャー1』の物語世界へスーッと入っていきましょう。
ここはポーランド発のダークファンタジーRPGとして名を馳せたゲームシリーズ。
その第一作となる『ウィッチャー1』は、2007年にCD PROJEKT REDからリリースされ、多層的な政治の暗部や差別構造、そして謎に満ちた怪物たちによって、とんでもない奥行きを持ったストーリーを構築しました。
今回は、そのあらすじをネタバレ込みで余すことなく、しかも結末までをたっぷり語ってみようと思います。
長文になってしまいますが、どうぞ家のチャイムが鳴ろうと、猫が足をまとわりつこうと、ちょっと待ってもらってじっくりお楽しみください。
ここから先は、
『ウィッチャー1』の物語を大きくネタバレ
しています。
これからプレイしようと予定されている方は、ご自身のタイミングに合わせて閲覧を検討してくださいね。
この記事では、重厚な世界観をともに俯瞰しながら、必要であれば
「ではここでもうひと呼吸ね」
といった感じで、まるで雲の上から場面を見下ろすように紹介していきます。
ここには、原作小説との関係やアニメ・ドラマ版との対比、またその後に発売された続編との繋がりも紛れ込んでいます。
気軽に読んでいただきつつ、隠された裏話や考察ポイントに触れていただけると嬉しいです。
ウィッチャー2のストーリーあらすじネタバレ!結末までチェック
ウィッチャー3のストーリーあらすじネタバレ!結末までチェック
スポンサーリンク
ゲラルトとウィッチャーの世界観
ウィッチャーとは何者か
ウィッチャーとは
怪物退治を専門
とする剣士の呼称です。
どこかのハローワークに「怪物退治人、月給制あり」なんて求人が出ているわけではなく、幼少期から苛酷な錬金術や薬草学、魔術の訓練を受け、最終的に“変異”と呼ばれる人体改造を突破したほんの一握りの者だけが名乗れる特異な存在。
生き残りの確率は笑えないほど低い
という、恐ろしくも儚い職業形態です。
この変異のプロセスにより、身体能力は普通の人間を超え、光量が少ない暗闇でも瞳が猫のように光って物を見られるようになります。
ただし人間としての外見的特徴は保ちつつも、それを超えたパワーと独自の身体特性を得ているがゆえに、世間の人々からはひと昔前のアイドルのように「キャー素敵!」と崇められるどころか、むしろ
「おっかない奴らだ」
「変な薬でイかれちまってる」
と恐れられる面が強い。
何でしょうね、ビジュアル的にはイケオジですけど、その強さの正体は怖い……
みたいな複雑な感情が皆の心を駆け巡るんでしょう。
『ウィッチャー1』の主人公、リヴィアのゲラルトもそんなウィッチャーの一人。
特徴的な白髪に鋭く黄味を帯びた瞳、洗練された身体つき、そして何よりクールな判断力が魅力です。
中身としては、女性にモテたり、時々辛辣な言葉を吐いたりしますが、根は優しく思いやり深い(はず)。
剣術だけでなく簡単な魔法(サイン)も駆使できるため、怪物退治のみならず、実質的に「人間のほうがよっぽどタチが悪い」場面でも活躍するのが彼の真骨頂です。
追加解説ウィッチャーの歴史と訓練
少し解像度を上げると、ウィッチャーというのは古の時代に人間が“怪物対策”として生み出した
実験的兵器の産物
とも言われています。
魔術師と錬金術師の手で見いだされた秘薬を使い、少年期の子どもを強制的に変異させる。
そこを生き抜けた子どもが大人になると、身体能力はもちろん毒への耐性も備えた“プロ”として歴史を渡り歩く。
その生存確率は数%なんて話もあり、
「やめときなよ」
と周囲が反対しても、運命に引き寄せられるようにウィッチャーになる子も存在する。
その背景には過酷な時代事情もあったりするのかもしれませんが、詳しく語られることは多くありません。
謎がまたそそられるわけです。
原作小説との繋がり
『ウィッチャー』シリーズは、ポーランドの作家アンドレイ・サプコフスキが執筆したダークファンタジー小説が元ネタです。
文学賞を総ナメにしながら人気を博し、後にこの小説をベースに様々なメディア展開が行われました。
その中に、CD PROJEKT REDが開発するゲーム版があるわけですね。
小説のゲラルトは、知的でユーモアもありながら、ときに皮肉っぽい。
女魔術師イェネファーや養子のシリとの関係、北方諸国と南方帝国の政治的緊張、古来のエルフやドワーフの文化、あれやこれやが深く描かれており、
「いいや、この複雑さが最高にいいんだ!」
とファンがむせび泣くほど濃厚な世界観となっています。
一方で、『ウィッチャー1』のゲームストーリーは小説の一部設定を継承しながらも、ゲームオリジナル展開が多いのが特徴です。
何しろ冒頭で
「ゲラルトは死んだと思われていたのに、生きてたうえに記憶喪失になってる」
という展開がドンッと来るわけで。
これにより、プレイヤーはゲラルトの過去を知らずとも問題なく物語に入り込めるし、小説ファンも
「どうやって生き延びた!?」
と興味津々になります。
追加解説小説との相違点
小説の終盤付近でゲラルトはある事件を機に死んだとされるのですが、ゲームではそれが
「どういう経緯かは分からないけどよみがえりました、しかも記憶が失せてます」
という新たなミステリーとして描かれています。
小説の流れを知る人からすれば
「やっぱりあの強運、普通じゃ終わらないと思った!」
みたいなツッコミが入りそうなところ。
逆にゲームから入った人は
「へえ、ゲラルトってこういう人なんだ」
と徐々に学べる仕組みになっているので双方のファン層を取り込む巧妙さを感じます。
プロローグケィア・モルヘンでの目覚め
記憶喪失のゲラルト
『ウィッチャー1』は、ウィッチャーの拠点「ケィア・モルヘン」でゲラルトが意識を取り戻すところから始まります。
倒れていたゲラルトを仲間が見つけて運び込んだら、
「あらま、おかえり。ただいま。そして…アンタ、記憶ないの?」
となったわけです。
白髪のウィッチャー仲間であるエスケルやランバート、そして女魔術師のトリス・メリゴールドが、彼をよく知る旧友として手助けしようとしますが、ゲラルト自身は何も覚えていないため、彼らとの関係性も
「どうやら仲良しだったらしいが、思い出せない…」
という微妙な距離感から始まります。
トリスに関しては、どうやら彼女とゲラルトはかつて良い仲だった…?
みたいな雰囲気がありつつも、本人(ゲラルト)が何も思い出せないという苦境。
最初から心をわしづかみにされる導入ですよね。
追加解説ケィア・モルヘンの由来
ケィア・モルヘンは“狼流派”ウィッチャーの拠点です。
かつては多数のウィッチャーが所属していたとも言われますが、時代の変遷や弾圧によって現在は廃墟同然。
外からの侵入が難しい立地なので、研究や訓練をひっそりと行っていた場所でもあります。
シリーズファンにとっては
「ここがあの伝説の?」
とワクワクが止まらない場所ですが、まだ序盤でゲラルトが混乱しているあたりも含めて、ここでのチュートリアル感はちょっと懐かしい空気が流れているように思います。
サラマンドラの襲撃
じっくりウィッチャー同士の再会を分かち合う間もなく、突然「サラマンドラ」という怪しげな犯罪組織がケィア・モルヘンを襲います。
リーダー格は魔術師アザール・ジャヴェッドと、その右腕で狙撃の名手「教授」。
「おいおい、こっちは今休憩ムードだよ?」
とツッコミたくなるところに容赦なくドカーンと来るわけです。
彼らの目的は“ウィッチャーの変異秘薬”を盗み出すこと。
どうしてそんなものが欲しいのか?
もちろん悪巧みに使う以外ないですよね。
サラマンドラは最初から周到な計画をしていたと見られ、拠点の結界を破って堂々と奇襲をかけます。
ウィッチャー側も必死に反撃しますが、秘密の材料は奪われてしまう。
トリスも負傷するし、意外にタフな連中で苦戦の末にサラマンドラは撤退していきます。
ここでゲラルトはまざまざと痛感するのです。
「ウィッチャーの秘薬」が何か大変な力を生むもので、それを奪われたら世界がとんでもないことになるかもしれない、と。
実際、変異によって得られる身体能力は人知を超えていますから、それを大量生産しようと思えば“人造の怪物軍団”みたいなものを作りかねない。
そうなったらもう普通の衛兵じゃ対抗できません。
結果、ゲラルトを含むウィッチャー仲間は
「このままではやばいぞ」
ということで、それぞれのルートでサラマンドラの行方を探るために旅立つことになります。
追加解説教授の恐ろしさ
教授はめちゃくちゃ冷静な狙撃の腕前を持ち、逃走時の計画性も優れ、結構なキレ者です。
ウィッチャーっていったら何をしても凄い能力の持ち主だと思いがちですが、教授の射撃能力は彼らすらも威圧するほどで、
「待って、なんで普通の人間がウィッチャーと同じくらい強いの?」
とプレイヤーをビビらせる。
これがまたサラマンドラの不気味さを際立たせます。
第1章ヴィジマ郊外 – 混乱の幕開け
ゲラルトの旅立ち
ゲラルトは、ひとまずテメリア王国の首都ヴィジマに向かいます。
サラマンドラの大拠点がそこに潜んでいるかもしれないし、都市のほうが情報を得やすいだろうという考えですね。
なお、ゲラルト以外のウィッチャー仲間も別方向へ分かれて手がかりを追うため、ここで一時的にチームはバラけます。
旅の道中、ゲラルトはさっそく事件に巻き込まれます。
ヴィジマ近郊の農村地帯では病が流行り、夜な夜な怪物が出て村人がやられているという。
そのうち魔物を退治できるのはウィッチャーしかいない、と頼られるわけです。
ゲームとしても、ここでクエストをこなしつつ経験値や資金を稼ぎ、サラマンドラの手がかりを探す準備を整えるステップになる。
追加解説最初のフィールド感
ゲーム的には
「はいはい、ここがチュートリアル第二段階ですよ」
みたいな感じで、昼夜サイクルを体感し、村人との会話で細かいサブクエストを拾い、怪物との戦闘を少しずつこなす流れ。
ウィッチャー1の世界では昼と夜でNPCの行動も変わり、夜はゾロゾロとホラー系クリーチャーが出てくるので、
「日が暮れたらどうする? 眠って朝にする? それとも夜のうちに恐怖と戦う?」
など、そこからすでに自由度の高いロールプレイが可能です。
夜な夜な出没する怪物たち
郊外では「獣(The Beast)」と呼ばれる凶暴なスペクターが出没します。
こいつはどうやら村人の悪意や後ろ暗い感情を吸収して肥大化しているらしく、単なる野生の化け物とは違う。
人の恨みや嫉妬、嘘、裏切りなどが積み重なると物理的に怪物を呼び寄せる――これがウィッチャー世界の怖いところですね。
もちろんウィッチャーとしては、剣やサイン(簡易呪文)で怪物を倒すのがお仕事なんですが、物語上は
「これって単純に『怪物を倒す』だけで解決できる問題じゃないかも」
というのが徐々に浮き彫りになる。
例えば、村人自身の隠した醜い秘密が獣の源泉になっている可能性があり、ただ退治するだけでは根治にならないかもしれない……。
このあたりから、すでに
「ウィッチャー世界、明るくないぞ。でも深みがあるな」
と思わされます。
追加解説怪物の種類と特徴
ウィッチャーの世界には吸血鬼、狼男、グール、スペクター系など多種多様なモンスターが存在します。
中には人間に近い知性を持つ怪物もいて、対話や交渉ができるケースもあるけれど、郊外で出現する怪物はほとんど会話が通じない。
「まずは攻撃パターンを読み解いて剣を振るべし!」
が基本となります。
あと、相手によって弱点が違うため、ポーションやオイルでしっかり準備する必要もあります。
アルビンとの出会い
その郊外でゲラルトは「アルビン」という不思議な力を持つ少年に遭遇します。
彼は孤児同然で、予知夢めいたビジョンを見たり、
「何かしら世界に影響を与える力がある」
と噂されています。
周囲の大人は「この子怖いわ」と疎んじがちですが、ウィッチャーであるゲラルトは
「こんな子どもを放っておけない」
といった使命感から、アルビンを何とか保護しようとします。
ただし、ゲーム上は
「アルビンを誰に預けるか」
「どの程度面倒を見るか」
といった選択肢が出る場面もあり、そこでの答え方によって後の展開に微妙に差が出る。
アルビンが重要なトリガーになり得る要素がいくつか散らばっているので、けっこう面白い仕掛けです。
追加解説アルビンの“力”の謎
アルビンが時折口にする“謎の言葉”や予知夢は、単なるファンタジー演出ではなく、
「大陸に潜む古代の力に近いかもしれない」
と言われています。
具体的な説明はウィッチャー1ではそれほど無いのですが、
「もしかして将来的に大物になるかもしれない…?」
と期待を抱かせるキャラです。
サラマンドラの影
ヴィジマに行くためには、門番に
「この郊外の事件は解決しました」
と示さねばならず、それにはまず獣の脅威や周辺の問題を片づける必要があります。
その過程で、ゲラルトはサラマンドラの活動痕跡を発見します。
どうやら村人を人身売買したり、密造に手を染めたりと相当な悪行を積み重ねているようで、
「ちょっと待って、こいつら普通のチンピラじゃないぞ」
という危機感がさらに募る。
ゲラルトとしては
「サラマンドラに変異秘薬を使われたら、こんな『獣』どころじゃない大騒動になるかも」
と懸念し、一刻も早くヴィジマ市内に入り、本格的に捜査を進めなきゃと焦る。
こうして郊外編をクリアした後、晴れて王都の門をくぐることができるわけです。
第2章ヴィジマ – 王都に渦巻く陰謀
王都の姿
ヴィジマはテメリア王国の首都であり、巨大な城郭都市。
貴族たちが住むエリア、商業で賑わうエリア、そしてスラム街的な貧民街が混在し、病が流行して閉鎖区域が発生していたりと、なんだかゴチャゴチャしています。
都会ならではの富と貧困、そして裏社会も入り乱れる複雑な空気が漂います。
ゲラルトはここでサラマンドラや、その協力者を探すべく、下水道から商業区まであちこち奔走。
ウィッチャーの直感を信じながら、時には情報屋に賄賂を渡したり、はたまた夜中に路地裏をうろうろして不審者を見つけたりと、まるで探偵気取りにならざるを得ない状況。
実際、ウィッチャーは
「怪物退治だけが仕事じゃないんだな」
と改めて感じさせられるパートです。
追加解説ヴィジマの内部構造
ヴィジマ市内は大きく分けて“商業地区”“寺院地区”“貴族街”“スラム”などがあります。
昼と夜で雰囲気がガラリと変わり、白昼の市場は人で溢れているのに、夜には酔っ払いと盗賊くらいしかいない。
そこに魔物が紛れ込むこともあるから油断できません。
ウィッチャー1では
「マップ規模が後のシリーズほど広くない」
と言われがちですが、当時としては十分入り組んだ街並みでしたし、クエストの量も盛りだくさん。
フレーミングローズ騎士団とスコイア=テル
ヴィジマに入り、さらに進めていくと「フレーミングローズ騎士団」と呼ばれる人間至上主義的な騎士団と、エルフやドワーフなど非人間族によるゲリラ組織「スコイア=テル」の激しい対立が表面化してきます。
もうバチバチです。
- フレーミングローズ騎士団:テメリア王家や保守派貴族の支援を受け、人間の秩序を守ると称して非人間族を攻撃します。
- スコイア=テル:人間に土地や権利を奪われ、長年迫害されてきたエルフやドワーフが武装蜂起し、権利を取り戻そうとする勢力。
ゲラルトはウィッチャーとして政治的中立を基本としていますが、物語が進むにつれて彼ら二勢力との関わりを避けては通れません。
騎士団がテロリスト扱いするスコイア=テルをどう見るか?
逆にスコイア=テルは過激な手段も辞さない革命派ゆえに、一般市民には迷惑行為をもたらすこともある。
どちらかを支援するか、どちらも突き放すか――プレイヤーの選択がクエスト展開や後のシナリオ分岐に影響を及ぼすのです。
追加解説対立の発端
背景には大陸の歴史的な戦争があり、
もともと先住民だったエルフやドワーフが人間に負けて領土や権利を奪われた
という過去があります。
フレーミングローズ騎士団は、それを「人間の正当な勝利」として捉え、今なお非人間族を抑圧する行動を正当化している。
一方、スコイア=テルからすれば
「我々を奴隷扱いにする人間側こそ悪」
であり、暴力に頼ってでも変革しなければ生き残れないと主張する。
どちらもそれなりに理由を抱えており、ウィッチャー1のダークファンタジーらしさを象徴する要素でもあります。
捜査の過程下水道やスラム街
ゲラルトはサラマンドラを追いつつ、下水道やスラム街でモンスターと戦闘しながら証拠を集めていきます。
ヴィジマの下水道は結構迷路っぽくて、グールとか下水道専用の怪物がうろついているので油断は禁物。
スラム街では貧民が行き倒れていたり、盗賊が闊歩していたりと危険がいっぱい。
でもそこは、ポーション飲んで剣を振り回せば何とか……
と言いつつ、やっぱり情報は意外なNPCから得られたりします。
捜査を進めると、やはりサラマンドラはこの街の権力者ともつながっているっぽいという事実が浮上。
つまりただの山賊や闇組織ではなく、魔術師や貴族などのバックアップがある可能性が濃厚。
ウィッチャーの秘薬を悪用しようとする大きな陰謀が進んでいるとしたらゾッとしますよね。
追加解説クエストの広がり
ヴィジマではサブクエストも多彩で、
「花街での揉め事を解決して」
「闘技場でならしたい」
「夜間にスリが横行しているから何とかして」
等、よくまぁこんなに事件があるなと驚くほど。
普通のゲームなら
「最初から最後までメインストーリー一直線だ!」
となりがちですが、ウィッチャー1ではかなりの寄り道が可能で、それらが世界観の厚みにもつながっているのが魅力です。
自由都市ノヴィグラドとの違い
後の『ウィッチャー3』で登場する巨大都市ノヴィグラドと比べると、ヴィジマはどうしてもスケール感で劣ります。
でも当時はこれだけで十分驚きがあったし、むしろ城郭都市としての閉塞感や中世の衛生状態がよろしくない雰囲気がリアルに描かれていたと言えます。
ノヴィグラドが“大都会の自由都市”なら、ヴィジマは“王国の首都”として治安の面でも厳格。
どちらも一長一短、比較してみるとシリーズ全体の都市観が深まっておもしろいですよね。
第3章政治と陰謀の深層 – 騎士団長、王、魔術師たち
テメリア王 フォルテストとの面会
捜査の段階で、ゲラルトはとうとうテメリア王フォルテストと会える機会を得ます。
そもそも王としては、
「自分の国で何やら不穏な組織が暴れているうえ、怪物も出まくりだし、いい加減どうにかせねば」
と考えていて、そこへウィッチャーの実力が加わるのは悪い話じゃない。
フォルテスト王は
「フレーミングローズ騎士団ともうまく連携して、スコイア=テルも押さえつけつつ、サラマンドラ問題を解決してくれ」
と依頼してきますが、ゲラルトにしてみれば
「ウィッチャーは政治に関わらない」
のが基本ポリシー。
やむを得ず国のために働く形は取っても、べったり協力する気はありません。
ここで微妙な駆け引きが生じるわけです。
追加解説フォルテスト王の性格
フォルテストはカリスマ性もあり、決して悪王ではないのですが、個人的スキャンダル(愛人とか私生児とか)を抱えていたり、周辺諸国との外交問題に頭を悩ませていたりで、あまりゆっくりゲラルトの話を聞いている余裕もなさそう。
彼は
「ウィッチャー、お前に頼むしかないのだ」
と語りながらも、自らがどう動くかを探っている印象があり、シリーズを通してその政治観がどんどん掘り下げられていきます。
騎士団長との関わり
フレーミングローズ騎士団を率いる騎士団長は、敬虔で高潔な指導者に見えます。
しかし物語が進めば進むほど、
「あれ、この人が実は一番ヤバい人じゃないか?」
という疑念が強まる。
実のところ、彼こそがサラマンドラと裏でつながり、
“ウィッチャーの秘薬”を利用して自身を変異させ、人間を超えた支配者になろう
という大それた野望を抱いているのです。
非人間族を排除すると言いつつ、自分が化け物じみた力を欲するって、なんかめちゃくちゃ皮肉ですよね。
騎士団長は終盤までその正体を巧妙に隠し、スコイア=テル掃討や街の治安維持を行う“正義の味方”を装っています。
プレイヤーがそれを知ってどう行動するか、あるいは知らないまま協力してしまうかで、ストーリーの味わいが変わります。
追加解説騎士団長の思想
彼は
「人間が最強であるべきだ」
と強く信じており、ウィッチャーの力を吸収すれば誰より強い人間になれると確信している。
要するに、排他的な優生思想を究極に推し進めた姿と言えるでしょう。
そこがゲーム終盤の衝突において、もっともダークファンタジー色を濃くさせています。
トリス・メリゴールドの存在
『ウィッチャー1』では、女魔術師トリス・メリゴールドが重要な支えとなります。
ケィア・モルヘンで負傷しながらもゲラルトを助け、その後ヴィジマでも情報収集や魔術サポートを行ってくれる存在。
彼女は王宮にもパイプがあり、そこからゲラルトの行動をサポートしてくれるわけですね。
ただ、トリスとゲラルトの関係性は微妙。
過去にどうも深い仲だったらしいけれど、ゲラルトは記憶を無くしている。
一方、トリスはゲラルトへの好意がまったく消えておらず、しかも小説を読んだ人には
「いやいや、ゲラルトにはイェネファーという運命の女性が…」
と心の中で葛藤が生まれるポイント。
ウィッチャー1ではイェネファーは出てきませんが、その存在を匂わせるようなシーンはあります。
また、ゲーム内でアルビンをどう扱うか、トリスに預ける選択肢などが出てくる場合もあり、彼女とゲラルトの距離がさらに近くなるイベントが発生することも。
ロマンス要素を強く押し出してはいないものの、ウィッチャー1なりのささやかな恋愛ドラマは、ファンタジーの殺伐とした空気をほんの少し柔らかくしてくれます。
追加解説恋愛要素の扱い
ウィッチャー1ではカード収集要素(女性キャラとの関係を深めると専用カードが得られる)なんてシステムがあり、当時はちょっとした話題になりました。
現代的な倫理観で見ると
「うーん、どうなんだろう…」
という点もありますが、当時は
「あら可愛いイラストが集まる~」
と喜んでカードゲットに走るプレイヤーもたくさん。
トリスとも一定条件を満たすとそういう特別なイベントが発生するんですね。
魔術師連盟や他の勢力
ウィッチャーの世界には複数の魔術師団体(例えば魔術師会合やロッジなど)が存在します。
ウィッチャー1でも断片的に言及される程度ですが、アザール・ジャヴェッドのように“闇落ち”した魔術師もいるので、もしかすると大陸にはまだまだ怪しい連中がいるかもしれないと思われます。
ジャヴェッドはサラマンドラのリーダー格にして、大規模な変異実験を牛耳る魔術師。
彼がどこからその禁術や秘薬の情報を得たのか、なぜここまで強力な魔力を備えているのかなど、詳しい背景は断片的ですが、いずれにせよ
「こいつ相当危険」
という評価に落ち着くのは間違いありません。
追加解説魔術師の利権
王や貴族に仕える宮廷魔術師から、ロッジと呼ばれる秘密結社的な集団まで、その活動範囲はかなり幅広いです。
魔術師は大陸の政治を裏で操る影の支配者、なんて陰謀論もちらほら。
ウィッチャー1ではそこまで踏み込みませんが、ジャヴェッドの暗躍を見るに、魔術師界隈の権力争いは水面下で熾烈なのかもしれません。
第4章スコイア=テルとの接触 – 種族間対立の行方
エルフやドワーフが抱える苦悩
物語中盤で、ゲラルトはスコイア=テルと本格的に接触することになります。
非人間族のゲリラ組織というと、パッと聴きは
「テロ集団…?」
と感じるかもしれませんが、彼らには彼らの正義や言い分がある。
人間に強奪された土地や権利を取り戻し、自由に生きたいと願っている。
歴史的にはエルフやドワーフのほうが先住民だったのに、後から来た人間に征服された……
何という悲しい現実!
スコイア=テルの指導者であるエルフのヤーヴィンなどは、ゲラルトに対して
「人間とは分かり合えない」
「我々は最後の戦いをするのみだ」
と語り、場合によってはゲラルトを仲間としてスカウトしてくることもある。
政治に深入りしたくないウィッチャーだけど、
「このまま黙って見過ごすこともできないな」
と考える可能性は大いにあるわけです。
追加解説エルフと人間の歴史
実は大昔、エルフには高度な文明がありました。
しかし人間が大陸に流入して戦争が起き、エルフやドワーフは敗北。
長寿のはずのエルフも、
「人口減少によって絶滅が近いかもしれない」
と嘆く者もいます。
ここまで追い詰められれば、
「やむを得ず武装蜂起する」
というのも分からなくはない。
彼らの目から見れば、人間による搾取や差別はあまりにも根深いわけです。
フレーミングローズ騎士団 vs スコイア=テル
スコイア=テルが大々的なテロ行為に踏み切ると、フレーミングローズ騎士団が武力で鎮圧にかかります。
これがヴィジマ市街や周辺地域を巻き込む騒乱へ発展し、路地裏から田舎村まで血生臭い事件が続発。
このままでは市民の安全もままならない状況に。
ゲラルトがどう動くかによって、
「どちらかを助ければもう片方から敵視される」
「中立を貫けば双方から理解されずに孤立する」
など、プレイヤーとして判断が迫られる局面が多々訪れます。
やや政治っぽい選択に見えますが、現実世界で言えば、
「うちには出資者がいるんで中立は選択肢ではない」
と会社上層部に言われるのとどこか似ていて、苦笑いが止まりません(ただの個人的想像ですが)。
追加解説中立の難しさ
ウィッチャーのモットーは「怪物退治はするが、人間同士の争いには関わらない」。
しかし目の前で非人間族への虐殺が行われれば、さすがにゲラルトも知らん顔できないし、助ければ今度は騎士団から
「お前は反逆者か」
と責められる。
ここに生じるジレンマこそが、本作の醍醐味と言ってもいいでしょう。
選択がストーリーに及ぼす影響
ウィッチャー1は選択肢によるストーリー分岐をかなり推しているゲームですが、実は“結末そのものを大きく変える”までには至りません。
終盤の展開で多少変わる部分はあるものの、最終的に「黒幕は誰で、ゲラルトはどう動くか」は同じ方向に落ち着きます。
それでも、道中のクエスト内容やNPCの運命、会話の展開が異なり、
「自分はこういう世界を見たんだな」
というプレイヤーの満足感に繋がるのが魅力です。
スコイア=テル寄りのルートを通った場合には、後半ヤーヴィンが手助けしてくれるとか、逆に騎士団を支援したら別のイベントが開く、といった仕掛けが随所にあります。
追加解説分岐の程度
たとえばスコイア=テルを助けた結果、ある村での評価が上がる一方、騎士団の隊長からは嫌われる場面が発生する。
また戦闘時に援軍として駆けつけるメンバーが変わるといった細部の違いも大きく、RPG的なリプレイ性を生むわけです。
プレイヤーによって“俺のゲラルト”像が変わるのも面白い点です。
第5章サラマンドラ本拠地への突入 – アザール・ジャヴェッドとの対決
変異の秘薬を狙う野望
ストーリーが佳境に近づくと、サラマンドラがウィッチャーの変異秘薬を用いて“人間を強化する実験”を行っていることが判明します。
彼らは誘拐した人々に無理やり変異を施し、成功すれば最強の戦士を量産できるというヨダレが出そうな計画を進めているのです。
ウィッチャー仲間やゲラルトとしては、「やめてくれ~!」と全力で止めたくなるところ。
失敗すれば被験者は死ぬだけだし、成功したら成功したで制御不能の化け物ができそうだし、いいこと何もありません。
サラマンドラのリーダー格として立ちはだかるのが魔術師アザール・ジャヴェッド。
彼は相当優秀な研究者かつ魔術師であり、常識的な枠を超えた執念で変異研究を進めています。
ウィッチャー仲間にとっては人類に対する大犯罪、いや生態系を乱す究極の蛮行と言っても差し支えない。
結果的に
「これを阻止できるのはゲラルトしかいない」
と盛り上がってくるわけです。
追加解説変異実験の恐怖
ウィッチャーとして一人前に育つためには子どもの頃の訓練や試練を経て生き残らなければなりません。
大人に対して変異処置を施すなんて、リスクが何倍にもなるのは当然。
死ぬか狂うかで済めばまだマシ、下手をするととんでもないモンスターが誕生してしまう可能性も否定できない。
もしそんな軍団が作られたら…
テメリアだけでなく北方諸国全域が大混乱に陥るでしょう。
ジャヴェッドの魔術と教授の狙撃
サラマンドラには教授と呼ばれる暗殺専門の殺し屋もいて、クライマックスでは彼の狙撃とアザール・ジャヴェッドの強力魔術がタッグを組んできます。
どうやって同時に対処すればいいんだというくらい手ごわいコンビ。
プレイヤーはここで、拠点に突入する前にポーションや剣用のオイルをしっかり準備し、特定のクエストで仲間を得ておくなど入念な準備が必要です。
ウィッチャー1の戦闘はリアルタイムアクションではあるものの、タイミングクリックが独特で、しかも難易度が上がる終盤だと操作ミスが許されない。
ハラハラしながらコンボを決め、サインを織り交ぜて敵を倒す流れが、ここで最高潮に達します。
追加解説教授との再戦
序盤にケィア・モルヘンを襲撃した彼と再度ぶつかる場面では、単なる暗殺者ではなく“知略に長けた男”としての面が強調される場合もあり、サラマンドラ内部の内紛やジャヴェッドとの微妙な温度差が垣間見えるパターンもあります。
こういうキャラクター同士の駆け引きを想像するのも楽しいですね。
ボス戦魔術師アザール・ジャヴェッド
終盤のボス戦はアザール・ジャヴェッドとの一騎打ち(または教授との連戦)が大きなヤマ場。
強力な魔術をぶっ放してくるジャヴェッドに対抗するには、ゲラルトの剣術だけでなく、イグニなどのサインも駆使する必要があるでしょう。
ウィッチャー1の戦闘システムは、剣スタイル(強打・速攻・対集団)を状況に応じて切り替え、タイミングよくクリックすることでコンボを繋げる仕組み。
初見で混乱しがちですが、慣れると
「ふっふっふ、ここで強打スタイル~からのイグニ焼き!」
なんて華麗にキメると爽快です。
ジャヴェッドは魔物を召喚してくることもあるので、ヘタすると四面楚歌になる。
ここはプレイヤーの忍耐と根気ときっちり調合したポーションが物を言うという、ウィッチャーらしい攻略が求められます。
追加解説サイン活用例
アード(衝撃波)で敵を吹っ飛ばしたり、イグニ(火炎)で範囲ダメージを狙ったり、クエン(防御)で生存性を高めたりと、まるで厨二病のカッコよさを形にしたようなスキルがそろっています。
特に後半は敵の火力も高いので、ノーガード戦法ではかなり危険です。
賢く組み合わせることが肝要ですね。
アザール撃破後の衝撃の事実
激闘の末、アザール・ジャヴェッドを倒せば
「やった、これでサラマンドラも壊滅……?」
と思いきや、実は背後に真の黒幕が控えていたことが判明します。
そう、テメリア王国のフレーミングローズ騎士団長がすべてを裏で操っていたのです。
どうりで怪しいと思った!
ジャヴェッドはあくまで騎士団長の手先か、あるいは利用されていただけで、騎士団長こそがウィッチャーの秘薬の真髄を手に入れ、
「自分こそが新時代の支配者になる」
と本気で目論んでいる。
こうして次の章へ物語は移行します。
第6章雪山の決戦 – 騎士団長との因縁
テメリアを揺るがす反乱
騎士団長はもはやフレーミングローズ騎士団を率いて公然と暴走し始めます。
スコイア=テルも必死に抵抗し、王都ヴィジマ近辺は内乱状態へ。
フォルテスト王も手を焼くばかりで、ゲラルトとしては
「最終的には彼を止めるしかない」
という結論に至るのはもはや必然です。
騎士団長は自らも変異処置を施し、尋常ならざる戦闘力を得ているため、これから雪山での最終決戦が控えています。
物語的にもクライマックスの盛り上がりで、プレイヤーが鍛え上げてきたゲラルトのスキルと装備で挑む最高のタイミング。
天候は荒れ狂い、雪が吹きつける中での一騎打ちは胸が熱くなります。
追加解説スコイア=テルとの共闘か、騎士団か
プレイヤーがどの勢力に付き、どんな選択をしてきたかでこの最終戦に同行してくれる仲間が変わる可能性があります。
スコイア=テルを選んでいれば非人間族の仲間が駆けつけ、騎士団を選んでいれば騎士団内部で騎士団長を裏切るような展開があったり…
いずれにしても最終的に騎士団長が本性を顕すので避けて通れない衝突なのです。
ストーリーのピーク雪山での激突
雪山はウィッチャー1の象徴的なラストバトルステージ。
嵐のような吹雪の中、騎士団長が変異によって得た圧倒的なパワーを振りかざし、
「新時代の秩序をここに築く!」
などと高らかに宣言する。
私はプレイしながら
「いや、雪山でそんな演説しなくても…」
と思わずツッコミたくなりましたが、それほど彼もテンションが振り切れているのでしょう。
プレイヤーとしては、ここまで鍛えた剣技やポーション調合を駆使して、必死に応戦。
騎士団長は普通の剣撃だけでなく、ウィッチャーのようなサインや超反応を見せるシーンもあり、もはや人間の枠を超えた存在です。
そりゃそんな化け物を王にしちゃダメだろうということで、この決戦はウィッチャー1の最高到達点とも言えます。
追加解説雪山シーンの演出
当時(2007年頃)のゲームとしては、雪のエフェクトや音響効果がなかなかリアルで、冷たい空気感や足元の不安定さが伝わってきます。
まさにダークファンタジーのクライマックスにふさわしい背景。
ここに至るまでの選択や伏線が全て集約して
「騎士団長を倒すしかない!」
とプレイヤーの気持ちも盛り上がる仕掛けが見事です。
いくつかのルート分岐
最終的に「騎士団長を倒す」という骨子は変わりませんが、途中のルート次第でスコイア=テルのメンバーが加勢するとか、あるいは騎士団の一部がゲラルトに協力するなどの差が生じます。
どのルートを通っても、ウィッチャーとしての仕事を全うできる一方、それぞれの勢力に後味の悪さが残るのが本作らしい。
いわゆる
「この先どうなるんだろう……」
という不穏さを残したまま、ゲームはクライマックスへと突き進むわけです。
追加解説騎士団長撃破後の違い
もし騎士団と基本的に行動を共にしていたなら、その内部で生じる内紛を目撃するシーンがあったりしますし、スコイア=テル寄りなら
「非人間族が今後どんな暮らしをしていくのか」
を語るシーンが追加されたりします。
いずれにしてもゲラルトは単純に勧善懲悪で割り切れる立場ではなく、“自分の信念による決断”で結果を受け入れざるを得ない、という締め方です。
謎の暗殺者とウィッチャー2への伏線エピローグ
王への謁見と暗殺未遂
最終決戦後、ゲラルトはフォルテスト王のもとへ凱旋し、サラマンドラの脅威を除去した英雄として称えられます。
これで平穏が訪れる……
と思った次の瞬間、謎の暗殺者が王を狙って斬りかかる事件が発生!
ゲラルトがとっさに防ぎ、暗殺者と剣を交えるものの、そいつは妙にウィッチャーっぽい動きで、尋常じゃありません。
結局、謎のまま暗殺者が姿を消すか、あるいは倒せたとしても
「なぜ王を狙った? 何者なんだ?」
という疑問は残ったまま。
こうして『ウィッチャー1』は幕を閉じますが、これは実質的に「次作『ウィッチャー2』への大伏線」と言えるでしょう。
追加解説:暗殺者の正体
後の展開で掘り下げられる要素もありますが、当時プレイした人は
「誰なんだこの忍者みたいなウィッチャーは!?」
と混乱と興奮でいっぱいに。
ゲラルト自身が死から復活した存在なので、
「まさか別流派のウィッチャーにも似た奇跡が?」
とか、
「サラマンドラがまた新たに作りだした変異戦士?」
とか、ファンの間で憶測が渦巻きました。
『ウィッチャー2』への繋がり
エピローグの暗殺未遂シーンが終わると、次回作へのネタがバッチリ仕込まれたままです。
『ウィッチャー2』では早々に王暗殺を巡る大事件が勃発し、ゲラルトがその容疑を着せられる波乱の展開が待っています。
その導火線となるのが、このエピローグの伏線というわけ。
なので、ウィッチャー1を遊び終えたプレイヤーは大体こう思うはずです。
「このままじゃ終われない!続きやりたい!」と。
これがシリーズを追いかけるモチベーションにもなる。
怪物退治だけじゃない政治劇や大規模な陰謀が絡むのがウィッチャーの魅力ですから、十分に予告編としての役割を果たしているというわけですね。
追加解説王暗殺の影響
この世界では、王が暗殺されれば隣国との戦争リスクが一気に高まるなど、普通に大陸規模の混乱へと繋がります。
『ウィッチャー2』ではそういった要素がメインのストーリーとして描かれ、さらに大きな政治情勢にゲラルトが巻き込まれていく形になります。
選択と結果、差別と共存ウィッチャー1が描くテーマ
ダークファンタジーに宿る道徳の曖昧さ
見てきたように、『ウィッチャー1』の世界では「怪物退治」という表層的な仕事の裏側に、社会問題や人間関係の闇が蠢いています。例えば
- 村人の負の感情が実体化して怪物になる
- 権力者がこっそりウィッチャー秘薬を盗んで自分を怪物化しようとする
- スコイア=テルのテロ行為は、実は悲惨な歴史に根差した義憤からくるもの
プレイヤーはこれらの事件を通して、
「果たしてどこに正義があるのか?」
と悩まされるシーンが多い。
まさにダークファンタジーらしい、善悪二元論では割り切れない道徳的ジレンマ。
ゲラルトは“怪物退治のプロ”でありながら、時に人間こそが最悪の怪物に映る瞬間もある――そういう物語構造が非常に魅力的です。
追加解説道徳観のズレがもたらすドラマ
現実社会でも立場や文化の違いで
「これは正しい、あれは悪い」
という単純な話にならないケースが多々ありますよね。
それがファンタジー世界の種族間対立や魔術の歪みなどと合わさると、さらに混沌を極める。
プレイヤーはゲラルトの視点を借りて、そうした複雑さを垣間見るわけです。
ゲラルトはあくまで中立か
ウィッチャーの掟は、政治には関与しないこと。
けれど、本作ではどうしても政治や社会問題に直面せざるを得ません。
騎士団を手伝うかスコイア=テルを助けるか、それとも全員から一歩引いて中立を貫くか――。
これらの選択がプレイヤーに委ねられるというのもウィッチャー1の大きな特徴です。
このあたり、
「ああ、冒険ファンタジーだと思っていたら、しっかり社会派ドラマやってるじゃないの」
と驚く方もいるかもしれません。
開発陣はその葛藤を描くことで、
「ファンタジーは単にゴブリン退治だけが全てじゃないんだぜ」
と喝破しているようにも感じます。
追加解説ゲラルトのモノローグ
ゲーム中、ゲラルトは時折独り言や皮肉交じりのセリフで内面を垣間見せてくれます。
「政治に首を突っ込みたくはないが、放ってはおけない……」
といったセリフを聞くと、彼が
「自分なりの誇り」
「現実の問題」
の間で揺れているんだなと分かる。
その人生経験の深さを思うと、私としてはちょっと胸にグッと来るものがあります。
物語は“終わらない”終わり方
ウィッチャー1の最後で騎士団長を倒し、サラマンドラを壊滅させても、世界から完全に闇が消えるわけではない。
非人間族の差別も続くし、王国の政治混乱も決して収束したわけじゃない。
しかもエピローグで暗殺者が現れ、次回作に続く大きな謎まで投げかけるという終わり方です。
なんともやるせないような、しかし先が気になって仕方ないという絶妙な後味を残します。
この“尻切れトンボ感”が逆に
「もっとウィッチャーの世界を知りたい!」
と思わせるのです。
完全解決したわけじゃないけど、ゲラルトなりに目の前の大問題を一旦は解決している。
その不完全さが、シリーズ続編へと自然に繋がっていくのが魅力。
追加解説世界全体の行方
後のシリーズでは「ニルフガード帝国」という大国の侵攻も描かれますし、北方諸国の内ゲバも加速します。
ウィッチャー1はその前夜祭と言ってもいいほど“小さめの騒動”に見えるかもしれません(プレイ当時は十分大きな騒動でしたが)。
この世界は意外にも国際政治が緻密に設定されているので、ファンにとってはますます沼へハマる入り口になるのです。
システムとグラフィックスウィッチャー1のゲーム的特徴
タイミングクリック戦闘
ウィッチャー1の戦闘システムは独特で、一定のリズムでクリックすることでコンボが繋がり、より大きなダメージを与えられる仕組みです。
これは後の『ウィッチャー2』『ウィッチャー3』と比べるとかなり異なる設計で、賛否両論を生んだ要素でもあります。
でも慣れると、自分のクリックタイミングに剣のモーションがバチッとはまり
「チャキーン、チャキーン!」
とコンボが決まるのは気持ちいいですし、強打スタイルや速攻スタイル、対集団スタイルを切り替える戦略性も面白い。
ただ、初心者は
「なんでクリックしてるのに攻撃しないの?」
となって混乱するかもしれませんね。
追加解説操作モードの違い
ウィッチャー1には視点変更オプションがあり、三人称視点や見下ろし視点を切り替えられます。
これはプレイヤーの好みで選べるので、アクション重視なら肩越し視点、
パーティ的管理が好きならトップダウン視点、みたいな使い分けが可能。
後のシリーズでは見下ろし視点なんてないので、これも初代のレアな特徴と言えます。
アルケミー(調合)
ウィッチャーといえばポーションの存在も欠かせない。
戦闘前にハーブやモンスター素材を混ぜ合わせ、体力回復や暗視、毒耐性などを得られるポーションを作るのがウィッチャーの流儀です。
ただし飲み過ぎは禁物。
中毒度が高まって画面が白黒になり、ふらふらしながら戦うハメになります。
まるで寝不足状態みたいな。
さらに武器に塗るオイルや爆薬などもあり、それらを使いこなして敵の弱点を突くのが攻略の鍵です。
ウィッチャー1はこのアルケミーシステムがとても重視されていて、戦闘前の準備が楽しい人にとってはドはまりする要素となります。
追加解説ポーションの例
「スワロー」は自動回復を高める定番ポーション、「キャット」は暗所での視認性を上げるなど、状況に応じて使い分けが大切。
毒の耐性を高めるポーションもあるけれど、副作用も激しくなったりして、
「現実でもこんなの飲んだら絶対しんどいわ…」
と思いながら、ゲームならではの“良い塩梅”を楽しむ感じですね。
昼夜サイクルとNPC行動
ウィッチャー1には昼夜サイクルがあり、時間帯によって人や怪物の行動が変わります。
昼間は市場や商店が開いて賑わっているが、夜になると怪物が活性化し、NPCも家に引きこもるのでゴーストタウン化。
そこをウロウロすると危険度アップです。
こうしたシステムがあることで、まるで本当にその世界が生きているようなリアリティが生まれます。
クエストによっては特定の時間に出没するNPCやイベントがあったり、夜のみ受注できる仕事があったりするので、プレイヤーは
「じゃあ夕方まで宿屋で待機して夜の仕事に行くか」
なんてまるでリアル社会人スケジュールのような計画が必要になるわけです。
追加解説仲間NPCの動き
ウィッチャー仲間(ランバート、エスケル)やトリス、スコイア=テルの面々も夜は別の拠点で休んでいることがあったりします。
彼らに会いたいならこの時間帯に行かなきゃ、みたいなことを把握するのもRPGの味わいです。
リメイクや後続作品との関わり
ウィッチャー2・ウィッチャー3への繋がり
本記事でネタバレしているとおり、『ウィッチャー1』はシリーズ最初の作品にして、実は“まだ小規模”とも言える物語。
そこから『ウィッチャー2』では王暗殺の嫌疑をかけられたゲラルトがさらなる政治の闇に飲み込まれ、『ウィッチャー3』でついに世界規模の戦乱と“狂乱の白霜”という異界の脅威まで絡んでくるわけです。
ゲラルトの過去や、イェネファーやシリといった因縁の人物との再会など、壮大なドラマが待っている。
だからこそ、あらためてウィッチャー1をプレイしておくと
「なるほど、最初はここから始まっていたのか!」
と感動できるわけです。
エンディングの暗殺者が後々どう出てくるのかも含めて、シリーズに繋がる太い幹をここで感じ取れるでしょう。
追加解説ウィッチャー2の政治激変
ウィッチャー2のオープニングで、テメリア王フォルテストが暗殺され、ゲラルトが容疑をかけられる衝撃展開がドーンと来ます。
これはウィッチャー1のエピローグで暗殺者が示唆されていたからこその事件で、
「ああ、やっぱり大変なことになってる」
とプレイヤーを震え上がらせたものでした。
2022年発表のリメイク
CD PROJEKT REDは2022年、Unreal Engine 5を用いて『ウィッチャー1』をリメイクするプロジェクトを発表しました。
これはかなり大きなニュースで、当時のファンは興奮で夜も眠れなくなったとかならなかったとか。
特に初代独特の戦闘システムや操作感をどう現代風に仕立て直すのか、そのポイントには大いなる期待が寄せられています。
グラフィック表現やオープンワールドの拡張はほぼ確実として、ストーリー自体は尊重されつつも、一部イベントの再構築やリファインが行われる可能性もあるでしょう。
とにかく、初代ウィッチャーを今風の美麗ビジュアルで遊べるなら、シリーズファンにとってこれ以上ないご褒美ですよね。
追加解説リメイクへの期待
『ウィッチャー3』で確立された滑らかなアクションバトルを初代に組み込み、かつオリジナルの良さを損なわない形に仕上げてくれたら最高。
クエンやアードを使うときのエフェクトも現行ハードなら段違いの迫力になるでしょうし、オープンワールドでケィア・モルヘンが完全再現されたら堪りません。
「アラフォーになったら絶対にもう一度ゲラルトに会いたい!」
と思っていた方々には嬉しい限り。
ほんの少しだけガス料金の見直しという日常の選択
さて、ゲラルトの物語はダークで壮大で、モンスターも政治闇も登場しますが、我々の身近な世界にも意外と
「こっそり背後で何か良からぬことが…!」
ってケースがあるかもしれません。
私が思い当たるのが“プロパンガスの料金”。
これね、私も検針票を細かく見直すまでは知らなかったのですが、
いつの間にかガス会社が料金を上げていた
なんて話があるそうです。
サラマンドラほど悪質ではないものの、知らない間にじわじわ家計を圧迫すると考えると、なんだか怖いですよね。
そこで、エネピというサービスを使ったら、複数のガス会社を比較できて
「なんと、我が家は月に〇〇円も損していた…」
なんてことが判明。
変異秘薬までは盗まれませんが、生活費が知らず知らずのうちに吸い上げられる感覚は
「こっそり値上げだなんて…小規模サラマンドラかい!」
と愚痴りたくなる。
とりあえず私も夫に相談してガス会社を変更しようかと考えました。
現実世界ではモンスターとの白熱バトルはありませんが、こういった日常的な“闇”は自衛が大事。
ゲラルトも
「隙を見せたらダメだ、変異秘薬が盗まれるぞ」
と言っていた(かもしれない)ので、見直しが可能なところはしっかり対策しておきたいところ。
>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から
『ウィッチャー1』がもたらす深い余韻まとめ
『ウィッチャー1』は2007年当時としては驚くほど重厚なRPGでした。
記憶喪失のゲラルトが徐々に過去を思い出しながら、同時にサラマンドラという危険な組織を追い詰め、さらに王国の政治や非人間族の対立にも否応なく巻き込まれていく。
そこには安易な勧善懲悪の構図は無く、プレイヤー自身の選択が細かい結果を生み出していく奥深さがありました。
物語のおおまかな流れとしては
- ケィア・モルヘン襲撃でウィッチャーの秘薬が盗まれる
- ヴィジマ郊外で怪物退治と捜査を行い、サラマンドラの影を追う
- 王都ヴィジマでのフレーミングローズ騎士団とスコイア=テルの対立
- サラマンドラ本拠地への突入とアザール・ジャヴェッドとの激突
- 騎士団長の野望が明かされ、雪山での最終決戦へ
- エピローグで暗殺未遂事件が起こり、『ウィッチャー2』への伏線が貼られる
という大筋で進みます。
各章でいくつもの選択肢があり、それによってキャラクター同士の関係やイベント展開が微妙に変わります。
すべてのルートを知るには何度かプレイする必要があり、そうしたリプレイ性の高さも魅力でした。
シリーズ全体を眺めると、『ウィッチャー1』はその後の『ウィッチャー2』『ウィッチャー3』を繋ぐ基礎作りになっていることが分かります。
とりわけ、エピローグの暗殺未遂が次回作の火種になるのは明白ですし、本作で提示された“人間同士の争い”や“種族間の問題”は、後の大きな戦争や国際的な陰謀の一部に発展します。
もしウィッチャー1をまだ未プレイなら、ぜひ怪物退治だけでなく村人や政治家、エルフやドワーフとの会話にも耳を傾け、じっくりと世界の闇を味わい尽くしてみてください。
きっと
「やばい、こんなに濃いゲームだったのか…」
と嬉しい悲鳴を上げることでしょう。
追加解説ウィッチャー1エンハンスドエディション
当初リリースされたウィッチャー1は、
長めのロード時間やバグが散見される
など少々荒削りでした。
しかし後に発売された「エンハンスドエディション」では、翻訳やロードが改善され、新規アドベンチャーの追加やバグ修正などが施され、かなり遊びやすくなっています。
今からプレイするなら、断然エンハンスドエディションがおすすめ。
一度挫折した方も、最新版なら快適に遊べるかもしれません。
なお、現実世界に目を向けると、私たちの身近にも
“不気味な値上げモンスター”
が潜んでいることがあります。
プロパンガスの料金をはじめ、水道光熱費の細かいところを見直してみると、
「えっ、いつの間にこんな金額になってるの?」
なんてことも。何かと物価上昇の激しいご時世、ウィッチャー的な鋭い嗅覚で身を守るのも重要です。
たとえばエネピを使えば、各家庭のガス料金を比較できるので
「もしかしてうち、ガス会社を変えたらウィッチャーばりに節約できるんじゃない?」
なんて気づけるチャンスがあるかもしれません。
日常の中の“選択”が実は大きな影響を及ぼす…
というのはゲラルトの冒険とも少し似ていますよね。
>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から
終わりに
『ウィッチャー1』のストーリーは、発売から十数年を経てもなおダークファンタジー好きの心を掴んで離しません。
記憶喪失のゲラルトが自分の過去を探りつつ、異端の組織サラマンドラを追い、騎士団長という黒幕を倒し、しかし全てが解決したわけではない――この不完全な解決と次回作への期待感こそ、後の“ウィッチャー・サーガ”の始まりを強く意識させます。
もしあなたが
「ウィッチャー3から始めて、1は古いから未プレイだった」
という方なら、逆戻りして初代に挑戦するのも絶対にアリ。
ちょっと操作に戸惑うかもしれませんが、それだけに懐かしいRPG感を味わえて、新鮮な発見があるはずです。
また、リメイク版がどのように仕上がるかも楽しみですし、
「そのうち最新技術で変わったウィッチャー1を遊べるなら、今からワクワクが止まらないぞ」
という方は私と同じく心待ちにしましょう。
…そして、どうか皆さん、怪物が現れずとも日常の中にある
「なんかお金が減ってる気がする…?」
みたいな闇にもお気を付けください。
気づいたら財布がカラッポ…
という結末ほど悲しいものはありませんから。
私の場合は、家事・育児・仕事でバタバタしながら、「ウィッチャーごっこ」で気合を入れつつ、光熱費にも敏感になりました。
ゲラルト並みの洞察力を発揮して、ぜひエネピとかで比較してみると良いのではないでしょうか。
ともあれ、ここまで長い記事を読んでくださり、ありがとうございました。
これが少しでも『ウィッチャー1』の奥深い世界に興味を持っていただくきっかけになれば幸いです。
見てのとおり、怪物退治の裏には必ず“人間の心の闇”がある。
それをどう乗り越えるかはプレイヤー次第。
ぜひあなたの手で、ゲラルトの物語を完結させてみてください。
そこから先、何が待ち受けているかは…もうあえて言いますまい。
どうぞ、最高の冒険を。
そして、賢い選択で日常を安定させることもお忘れなく!
ここに記したすべてが、きっとあなたの“現実とファンタジーの境界”を少しだけ揺さぶってくれるはずです。
>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から
ウィッチャー2のストーリーあらすじネタバレ!結末までチェック