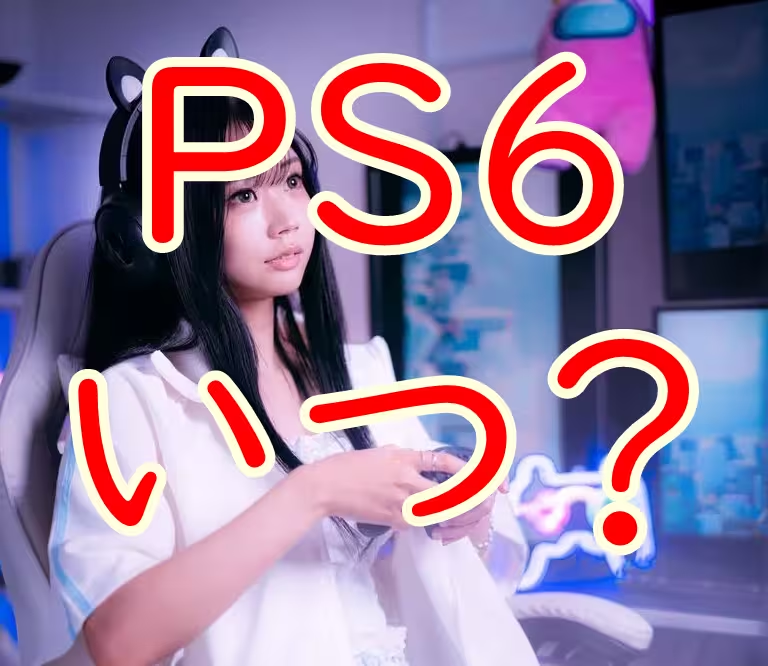ふと気づけば、私の家族にも
ゲーム大好き人間
が勢揃いしておりまして。
食卓で
『あの新作は買うべきか?』
と盛り上がるのが日課です。
そこへ来て、次なる世代の目玉機種と囁かれている「PlayStation 6」(以下、PS6)の噂が、ますます我が家の興味をかき立てているというわけです。
子どもが
「週末はゲームしていい?」
と期待に胸を膨らませ、夫は
「いやいや、先に値段が気になるだろ?」
と現実路線。
でも私は、この忙しい合間をぬって、ひそかに
「PS6が出たら、楽しみの幅がぐっと広がりそう~」
と期待を抱いております。
そこで今回は、PS6の発売時期から価格、スペック、さらには家計を圧迫しないためのアイデアまで、丸ごと深掘りしてみました。
日々の生活をやりくりしつつ、“次のゲームライフ”をどう設計するか、一緒に考えてみませんか?
スポンサーリンク
7年サイクルの伝統と外部要因PS6発売日はいつ頃か?
過去のPlayStationシリーズから見るリリース周期
PlayStationシリーズは、
ほぼ7年サイクル
で新モデルを投入してきた歴史があります。
PS3(2006年末)からPS4(2013年末)まで約7年、さらにPS4(2013年末)からPS5(2020年末)も約7年と、見事に「7」の刻印が押されているわけです。
こうした実績から逆算すれば、PS5が2020年にデビューしているので、
PS6の登場は2027年頃
になるんじゃないか――というのが有力な説。
とはいえ、昨今は
- 半導体の供給不足
- 世界的な物流混乱
といった予定通りに進まない要素が増えています。
PS5も発売時期こそ大きくブレなかったものの、初期在庫の不足で入手しづらい日々が続きました。
もし次世代機開発の最中に同様のトラブルが起きれば、PS6のリリースも前倒し・後ろ倒しなど、流動的に変わりうるかもしれません。
さらに、PS5 Pro の発売がありました。

ソニーとしてはPS5 Proをしっかり市場に定着させた上でPS6を出したいはず。
つまり、発売の優先順位やタイミングにも影響しそうです。
競合他社や市場の動向が与える影響
ソニーのライバルである任天堂は、2025年頃に「Switch 2(仮称)」を出す期待感が高まっていますし、マイクロソフトも「次世代Xboxはどうなる?」と業界内で取り沙汰されています。
競合他社が早々と新ハードを発表してしまえば、ソニーも焦って対応を急ぐかもしれません。
とはいえ、先に出して供給不足に陥るよりも、かつての反省を活かして安定供給できる時期を狙う可能性は高そうです。
部材調達の読みを外して“発売日に店頭に並ばない”なんてことになれば、ファンにとってはつらい待ち時間が続きますからね。
だからこそ、例の「7年周期」という伝統をベースに、市場と世界情勢を睨みつつベストなタイミングを探るのではないでしょうか。
高騰リスクと複数モデル展開の可能性PS6の価格
さらなる値上がりは避けられない?PS5からPS6へ
PS5の発売時価格は、ディスクドライブ付きモデルが49,980円(税別)、デジタルエディションが39,980円(税別)でした。

だけどその後、為替レートやら原材料費の高騰やらの影響で、実売価格が
地域によって上がるケース
が見られています。
この延長線上で
「じゃあ次のPS6はさらに上がるのか?」
という連想が働くのも無理はありません。
中には
「6~7万円程度じゃ済まないのでは?」
という話も。
さらにコアゲーマー向けの最上位モデルが用意されるとすれば、10万円オーバーもあり得そうです。
こんなご時世ですから、
「給料はそう簡単に上がらないし、ゲーム機だけ右肩上がりなんて困るんですけど!」
という叫びがどこかでこだましていそうな気もします。
複数モデル展開の合理性
マイクロソフトは、Xbox Series X|Sという形で、高性能版と廉価版を同時展開し、多様なユーザーを取り込む戦法をとっています。
ソニーもPS5でスタンダードエディションとデジタルエディションを出し、ある程度の価格差をつけました。
PS6ではより明確に
- 超高性能版
- 手頃なエディション
の二本立てをする可能性が高いと思われます。
コアゲーマーは多少高くても最高のスペックを求める傾向がありますし、ライトユーザーはむしろ
「安く買えればOK」
と考えます。
PCゲーム市場でも20万円くらいのゲーミングPCを普通に買う人たちが増えていますし、そういう意味では10万円台のゲーム機が出てもおかしくない。
ソニーがどのくらい強気の値付けをするかは、今後の供給状況やユーザーの財布の紐次第、といったところでしょうか。
CPUやGPUの進化とVR/ARの可能性PS6のスペック
AMDの新アーキテクチャを採用か
PS5はAMDのZen2をベースにしたカスタムCPUとRDNA2ベースのGPUを積んでいますが、PS6ではもっと新しい世代
Zen6相当のCPUやUDNAと呼ばれる最新GPUアーキテクチャ
が搭載されるのでは?と言われています。
CPUのマルチコア性能がアップすれば、一度に処理できる作業量が増え、大規模なオープンワールドの描画やAI制御がさらにスムーズに。
GPU性能が大幅に高まれば、4K・8Kクラスの高解像度や120fps以上の超滑らかな映像、あるいは光の反射・陰影をリアルに表現するレイトレーシングのクオリティが大きく進化するでしょう。
超高速SSDとメモリ拡張
PS5のウリの一つだった高速SSDによるサクサクロードは、一度体験するともう戻れない快適さ。
PS6も、このSSD性能のハードルをさらに上げてくると見られています。
データの読み書き速度をもっと早くし、ゲームのシームレス化を加速させることで、「次のステージのロードを待つ」みたいな作業がほぼ消滅する、なんて日も夢ではありません。
また、SSDの容量そのものも重要です。
PS5でも大容量のゲームを入れようとすると、どんどんストレージを圧迫してしまいます。
PS6時代は4Kや8Kの超高精細テクスチャが当たり前になり、データサイズがさらに肥大化するはず。
2TB~4TB、場合によってはそれ以上を標準搭載してくれるとうれしいですが、コストとの兼ね合いはなかなか難しそうな気もしますね。
VR/ARやクラウド技術の強化
PSVR2がすでにPS5向けに投入されたように、ソニーはVR領域にも力を入れています。
PS6ではケーブルレス化や高解像度化が進んだ新型VRヘッドセットが登場し、さらに没入感の高いバーチャル体験ができるかもしれません。
AR(拡張現実)方面でも、空間認識技術と組み合わせて斬新な遊び方を模索しているのでは?と想像が膨らみます。
クラウドゲーミングも、マイクロソフトのGame Pass戦略などに対抗すべく、ソニー独自の強化を図るはず。
ローカル処理とクラウド処理をうまく組み合わせることで、ユーザー体験をさらに幅広くしようという試みが本格化すると面白いですね。
ユーザーの移行をいかにスムーズにするか互換性とソフトウェア戦略

PS5・PS4ソフトとの互換性
PS5がPS4と高い互換性を持って登場したことは、多くのユーザーに喜ばれました。
ゲームソフトの資産がほぼそのまま引き継げるため、「前世代からの乗り換え」がスムーズになるわけです。
PS6でも当然、PS5との互換性を求める声は大きいでしょう。
とはいえ、ハードウェアアーキテクチャが大きく変わると
完全な互換を実現するのは難易度が高い
とも言われています。
PS3世代まで含むレトロタイトルをどう扱うのか、PS Plusを通じたクラウド配信やエミュレーションの強化で対応するのかなど、次世代機ならではのアプローチが期待されます。
キラータイトルや新IPの開発
ハードの性能だけじゃなく、結局は「魅力的なゲームタイトル」が命綱。
PS4・PS5の時代に『Horizon』や『The Last of Us Part II』、『ゴッド・オブ・ウォー』などが脚光を浴びたのも、ソニーのファーストパーティスタジオが持つ開発力が非常に強いからこそ。
PS6でも当然、大型フランチャイズの続編や新たなIPが計画されているはずです。
特に、新ハードの初期に専用ソフトをどれだけ用意できるかが、ユーザーの購買意欲を左右する大きなカギ。
もし発売直後のPS6に遊びたいソフトが少ない、という状況なら、
「PS5で十分じゃない?」
という声も出てくるかもしれません。
そのあたりをどうバランスするのか、ちょっとやきもきしちゃいますね。
ネットワークやAIとの融合ゲーム機以上の存在を目指すPS6
AIがもたらす新しいゲーム体験
最近はAI技術がめざましく発展し、ゲームの世界でも
「NPCの行動がリアルタイムで学習して変化する」
「広大なマップが自動生成される」
など、次世代の進化を予感させる要素が増えています。
PS6クラスの性能を持つハードなら、膨大なAI演算もリアルタイムでやってのけるかもしれません。
新しいAIアクセラレーション機能が追加されれば、さらに高度な物理演算やNPCの知能向上、プレイヤーに合わせた難易度調整などが実装される可能性も。
息子がサクッとクリアできるモードを選んだかと思えば、私や夫には絶望的難度を提示してくる――なんてドSなゲームがあってもよさそうです。
クラウド連携と“据え置き機”の概念
もしクラウドゲーミングとコンソール機のハイブリッドが進化すれば、PS6本体だけでなく、クラウドサーバー側のリソースも活用した超大規模なゲーム体験が生まれるかもしれません。
ローカル処理とリモート処理をうまく分散して、負荷を軽くしながら高画質を維持する、なんて技術が当たり前になったりして。
そもそも今は
- 据え置き機で遊ぶ
- 外出先はスマホで別ゲーム
という感覚が根強いですが、クラウドが発達すれば境界が曖昧になります。
PS6が“家に据え置く”だけでなく、どこでもアクセスできるゲームプラットフォームのハブとして機能する日は近いかもしれませんね。
生活コストにも配慮プロパンガスの話題を少しだけ
ゲーム機購入と家計管理のバランス
PS6がめでたく発売されたとして、やはり気になるのはお値段。
予想をはるかに上回る高価格帯に落ち着いたら、
「この先のご飯は納豆ご飯だけでいいや…」
なんて極端な節約モードに突入しそうで怖いです。
といっても、最新ハードの楽しさを家族でシェアできるなら、ある程度の出費は割り切って捻出したいところ。
そこで大事なのが、家計の無駄を見直すこと。
私はよく電気代を抑えるために、こまめにスイッチを切るのですが、意外と見落としがちなのがガスの料金。
特にプロパンガスは料金設定が事業者ごとに異なるうえ、
気づかないうちに値上げされている可能性
もあるという恐怖…!
プロパンガス変更サービス「エネピ」で浮いたお金を趣味に回す?
プロパンガスを自由料金制で使っている家庭なら、「エネピ」のようなサービスを使い、自分の住んでいる地域や使用状況に合ったプランを比較してみると、
思いのほか月々のガス代が安くなる
ケースがあります。
特に、私の周囲でも
「こんなにラクにガス会社変えられるんだ」
なんて驚いている人が増加中。
もしガス代や光熱費を少しでも削減できたら、その分をPS6の購入資金に回せるのでは?
家計を破綻させることなく、家族で最新ゲームを心置きなく楽しめるという理想のシナリオが待っているかもしれません。
電気・ガス・通信費など、見直せる固定費は意外とあるもの。
無理のない方法で趣味に投資する術を探ってみるのは有効ですよね。
>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から
まとめ
今からできる準備
PS6の登場は
2027年頃が有力
とはいえ、世界情勢やサプライチェーンの状況次第では前後する可能性があります。
価格も6万~7万円程度で落ち着くのか、それとも超ハイエンドなプレミアム版が10万円超で出てくるのか、まだ何も確定情報はありません。
ただ、PS5でも既に相当ハイクオリティなゲーム体験ができる時代ですし、PS4からのクロスジェネタイトルも続いています。
だからこそ、現世代機を遊び倒しつつ、次世代に向けて少しずつ貯金しておくのも悪くないはず。
子育てや仕事の合間を縫ってガス料金を見直すだとか、通信費を安くできないか工夫するとか、取り組むことはたくさんあります。
>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から
次の世代を創るのは私たちの期待と行動総括
ゲームファンとしては、PS6の情報を追いかけるだけでもワクワクが止まりません。
ソニーのファーストパーティスタジオが見せてくれるであろう新しい世界や、ハードの性能を限界まで引き出した美麗グラフィック、AIやクラウドとの連携による革新的な遊び。
すべてが“次世代感”をはらんでいると思うと、家事や仕事中までつい想像を巡らせてしまいそうです。
とはいえ、高価な買い物になるのは間違いなさそう。
そこでこそ、家計と相談しつつ、賢く固定費を下げていくアイデアが活きてきます。
やりくり上手になれれば、家族みんなで最新ハードを楽しむ道が開けるはず。
私としては、
「どうにかこうにか乗り越えて、新ハードを発売日にゲットするぞ!」
なんていう内なる闘志がふつふつと湧いてきます。
まだ公式アナウンスがない以上、実際にどんな仕様や価格になるか確定してはいません。
でも、その“曖昧さ”こそが今のゲームコミュニティを盛り上げている大きな理由でもあるのです。
「PS6が出たら何をやろう?」
と夢想する時間すら、おいしいお菓子と同じくらいの価値がある…
と私には思えてなりません。
今後も噂やリーク情報がいろいろ飛び交うでしょうが、どれだけ技術が進歩しても、最終的にゲームを楽しむのは私たちプレイヤー自身。
子どもと一緒に笑い合い、夫とも熱く攻略談義を交わしながら、私なりのゲーマー生活を続けていこうと、電車のホームでひそかに決意を新たにしている今日この頃です。
もしあなたも同じようにPS6への期待で胸を膨らませているなら、今のうちに情報をコツコツ集めつつ、生活費の見直しで“備え”を作っておくといいかも。
そうすれば、いざ新ハードが発表されたときに迷わず突撃できるはず。
私ももれなく、家計簿とニラメッコしながら準備を進めようと思います。
次世代の扉が開かれる日が、待ち遠しくてたまりませんね。