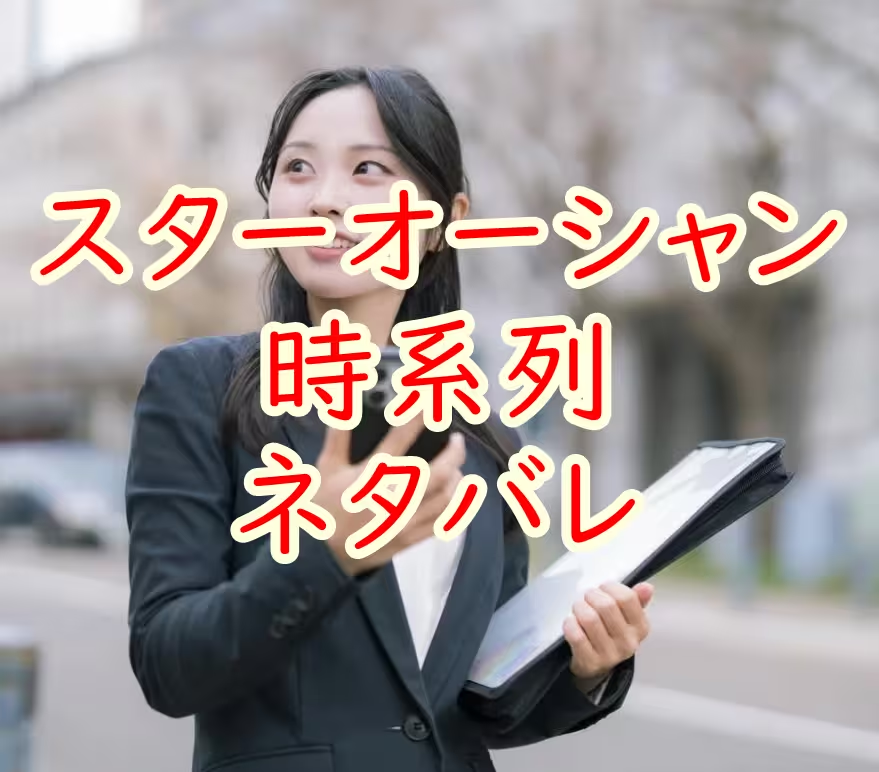果てしなく続く星の海を舞台に、“SF”と“ファンタジー”を融合した壮大な物語が展開されるスターオーシャンシリーズ。
1996年に初代作品が登場して以来、銀河連邦や未開惑星、異なる文化をもつ種族との交流など、ロマンの詰まった世界観で多くのプレイヤーを魅了してきました。
本記事では、そんなスターオーシャンシリーズを「宇宙暦」という独自の年号を鍵にしながら“時系列順”に徹底解説していきます。
といっても、発売順に並べると
初代スターオーシャン
→セカンドストーリー
→Till the End of Time…
という感じで進むのですが、時系列はけっこう前後しています。
「この作品はいったいどの時代に位置していたんだっけ?」
と混乱しがち。
そこで今回は、
物語の大きな流れを見失わないように、最古の年代から順に作品をピックアップし、主要テーマやネタバレを含めつつ解説する
という流れでご案内します。
さらに、後半ではシリーズ全体に通じるテーマや、2023年に発売されたリメイク作品の動向、そして
「なぜ今あらためてスターオーシャンが見直されているのか?」
なんて話にも触れます。
長くてボリューミーな記事になるかもしれませんが、壮大な宇宙の旅を思えば多少の長文もへっちゃら!
じっくりお付き合いいただければ幸いです。
なお、途中でちょろっと登場する“プロパンガス料金”の話は、本編とのギャップが面白いくらいの息抜き要素。
あくまでスターオーシャンのストーリー解説が本題ですので、
「そんなことよりスターオーシャンの話を!」
という方は軽く読み飛ばしてもらっても構いません。
それでは宇宙船のハッチを開け、いざ星の海へ飛び出しましょう!
スポンサーリンク
SFとファンタジーの融合スターオーシャンシリーズの基本構造
スターオーシャンシリーズは、「トライエース」が開発し、「スクウェア・エニックス(旧エニックス)」が発売しているRPGです。
最大のポイントは、銀河連邦のような高度に進んだ科学技術と、魔法や剣術が息づくファンタジー文化が同じ舞台に同居しているところ。
要するに、
宇宙船やビーム砲と、中世風の騎士や魔法使いが同じゲーム内で登場してしまう
という、ユニークな世界観が特徴です。
この状況がなぜ起こるかというと、作品内では「未開惑星保護条約」なるものが存在していて、科学技術の発展度合いが異なる惑星同士の接触にはいろいろ制限があるからです。
地球や連邦所属の先進惑星は超ハイテクを使いこなす一方、未開惑星の住民たちは中世レベルの生活を送っていたりするんですね。
でもシリーズを通じて何度か大きな事件が起こると、その未開惑星にも先進技術の影響がどかーんと入り込み、そこにいろんなドラマが生まれるわけです。
もう一点、スターオーシャンの重要なキーワードに「宇宙暦」という年号があります。
これは、西暦と同じ世界線でありながら、「西暦○○年のあとに宇宙暦が採用された」という設定。
シリーズ作品は、この宇宙暦を基準にした年代をそれぞれ持っています。
ところが、発売順は必ずしも年代順ではなく、後に発売された作品が実はもっと前の時代だったりして、シリーズ初心者にはややこしい面があります。
そこで以下の羅列のように「時系列が古い順番」に作品を並べてみると、歴史の流れが一気にクリアになります。
- 宇宙暦10年
『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-』 - 宇宙暦346年
『スターオーシャン1 -First Departure-』 - 宇宙暦366年
『スターオーシャン2 -セカンドストーリー-』 - 宇宙暦368年
『スターオーシャン ブルースフィア』 - 宇宙暦537年
『スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness-』 - 宇宙暦583年
『スターオーシャン6 -THE DIVINE FORCE-』 - 宇宙暦772年
『スターオーシャン3 -Till the End of Time-』
ここで気をつけたいのは、
初代『スターオーシャン』と『スターオーシャン4』の発売順が全然違う
ということ。
初代『スターオーシャン』は1996年発売、4は2009年発売なのに、時代設定では4がいちばん昔になる。
「そっちがプロローグ的扱いかい!」
と突っ込みたくなりますが、ストーリー的にそうなっているんだから仕方ありません。
それでは、いよいよこの順番に沿って、各作品の概要をネタバレ交えつつ紹介していきましょう。
宇宙暦10年スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-
作品の位置づけ
ここがスターオーシャンシリーズの時系列上最古の物語(ただし発売はシリーズ4作目)。
まさに“銀河連邦が成立する前”の時代が舞台です。
地球で第三次世界大戦が起こり、核戦争によって地表がボロボロになってしまったあとの世界(西暦2096年ごろ)で、人類がどうにかこうにか生き延びようと宇宙移民計画を始めたところからスタートします。
あらすじ(ネタバレ含む)
主人公はエッジ・マーベリックという若い宇宙飛行士。
地球が滅亡寸前になったため、“カルナス”という宇宙船で未知の惑星を探索し、新たな人類の生息地を確保するという壮大なミッションに挑みます。
仲間には同僚のレイミ・サイオンジをはじめ、いろんな種族や異星人も加わってくるので、パーティはなかなか多国籍軍団みたいになります。
そしてエッジたちは、惑星探査中に“グリゴリ”という謎の存在に遭遇。
グリゴリは惑星の生態系や文明に異常な干渉を及ぼす力を持ち、銀河全体に危機をもたらす可能性があると判明。
エッジは
「未開惑星の住民を自分のせいで巻き込んでしまう」
という痛恨の失敗も経験しながら、試行錯誤の末にグリゴリと戦うことに。
そこでの苦悩と決断が、のちに制定される“未開惑星保護条約”の倫理観に強く影響を与えます。
見どころ・テーマ
- SF色が強い作品
戦後の地球というポストアポカリプスなムードから始まるので、中世ファンタジー風の他惑星との文化ギャップが非常に際立ちます。 - 銀河連邦の原型
シリーズを通して重要視される銀河連邦が、まだ「生まれたて or 構想段階」というところに歴史的意義がある。
エッジの信念や行動がその後の大河ドラマへ繋がるわけですね。 - 未開惑星への干渉の是非
スターオーシャンシリーズ全体で何度も取り上げられる、
“高い技術を持つ星が低い技術を持つ星にどう関わるか”
というテーマが最初に顕在化する作品でもあります。
宇宙暦346年スターオーシャン1 -First Departure-
作品の位置づけ
こちらは1996年に初代としてリリースされたシリーズ最初のRPGですが、時代的には『4』より後になります。
PSP版『First Departure』やPS4/Switch版『First Departure R』でリメイクされており、遊べる環境が増えたこともあって、今でもプレイしやすいのが嬉しいところ。
あらすじ(ネタバレ含む)
舞台は未開惑星ローク。
中世ファンタジー的な生活が営まれる中、若い剣士ラティクスは、突然流行し始めた“石化病”に苦しむ故郷を救うために旅に出ます。
その道中で出会うのが、宇宙船のクルーであるロニキス・J・ケニーとイリア。
彼らは地球連邦所属で、
ローク住民からしたら未知の技術を持つ“何者か”
という存在。
彼らの調査で、石化病の原因は魔王アスモデウスの血によるものだと判明。
しかも手掛かりを得るためには、
過去のロークにタイムスリップ
しなければならないことに!
そうしてロニキスたちのSF技術で時間移動し、歴史の改変を懸念しながらも魔王を封じる方法を探す…
という流れが展開されます。
最終的には石化病を克服して平和が戻るものの、ロークをはじめとする未開惑星に先進技術を持ち込むことの善悪がしっかり描かれ、
“後々の銀河連邦や未開惑星保護条約への議論を加速させる事件”
として見ても面白いです。
ちなみにロニキスは後に『スターオーシャン2』で重要人物となるクロード・C・ケニーの父親として存在感を示すので、
「ここでの出会いが次作に繋がるのか!」
と、時系列を追う楽しさがアップします。
見どころ・テーマ
- SF×中世ファンタジーのコントラスト
ローク住民にとって、ロニキスやイリアのレーザー銃やワープ技術は「魔法以上に理解できない異能」。
そこの噛み合わなさが、物語序盤を盛り上げます。 - タイムトラベルという意外性
魔王アスモデウスという単語だけ見ると完全にファンタジーですが、タイムゲートで時空を越える展開があるからこそ、スターオーシャン的な科学+魔法の融合世界が際立ちます。 - キャラクターの運命とシリーズへの布石
後の作品(『2』など)で明かされることとの繋がりを知っておくと、
「あれ、あのケニーって…」
とニヤリとできるのが時系列プレイの醍醐味です。
宇宙暦366年スターオーシャン2 -セカンドストーリー-
作品の位置づけ
スターオーシャンシリーズの中でも屈指の人気と知名度を誇るのが、この『スターオーシャン2 -セカンドストーリー-』。
1998年発売ですが、2023年11月にはリメイク版『スターオーシャン セカンドストーリー R』が登場し、大いに盛り上がりを見せています。
時代的には前作から20年後、宇宙暦366年が舞台になります。
あらすじ(ネタバレ含む)
主人公は地球連邦の士官候補クロード・C・ケニー、そして未開惑星エクスペルの少女レナ・ランフォース。
クロードはある事故でエクスペルへワープしてしまい、そこでレナに“光の勇者”と呼ばれてしまうことに。
実はエクスペルでは「十賢者」という謎の存在による天変地異が問題視されていて、伝説にある光の勇者が救うという言い伝えがあったわけです。
こうして十賢者の脅威と対峙する形になったクロードとレナですが、その力は想像以上。
途中で惑星エクスペルそのものが消滅の危機に瀕し、救われた人々はエナジーネーデという別次元(?)の領域へと移動し、そこで十賢者と最終決戦を迎えます。
物語終盤になると、十賢者の目的や彼らの正体が明かされ、
「やっぱりスターオーシャンって単なるファンタジーじゃないな」
と気づくパワフルな展開が。
また、クロードは『1』に登場したロニキスの息子という設定なので、
「親の背中を追いつつも自分の道を選ぶ」
というテーマも描かれ、『スターオーシャン2』独特の青春ドラマ的な要素がしっかり染みます。
見どころ・テーマ
- ダブル主人公システム
クロード編・レナ編を選べることで、ストーリーの見え方が違ってくる。
仲間キャラクターとのプライベートアクションや好感度イベントが豊富で、奥深いロールプレイを楽しめる。 - 十賢者のインパクト
宇宙全体を滅ぼしかねない敵としてのスケール感、そしてその背景にあるSF要素が、作品をワンランク上の“スペースファンタジー”へと押し上げています。 - リメイク版の充実
『スターオーシャン セカンドストーリー R』はHD-2D風グラフィックや新システムの導入で、当時のファンはもちろん新規ユーザーにも魅力的。
戦闘のテンポや操作感が大幅に改善されていると評判です。
宇宙暦368年スターオーシャン ブルースフィア
作品の位置づけ
『スターオーシャン2』の直後(2年後)を扱う後日談的作品。
2001年にゲームボーイカラーで発売され、その後携帯アプリ版にもなりましたが、据え置きハード向けには移植されていないため、隠れたレアタイトル扱いでもあります。
舞台はエクスペルではなく、別惑星“エディフィス”が中心。
あらすじ(ネタバレ含む)
『2』の十賢者との戦いが終わり、平穏に戻ったと思いきや、新たな惑星エディフィスで不穏な現象が発生。
クロードやレナ、そして仲間たちが再度集結し、エディフィスの謎を解明すべく向かいます。
そこでは古代文明の遺跡や不思議な力が絡み合い、
“ブルースフィア”
というキーワードに象徴される不可解な現象が起きることに。
最終的に仲間たちの活躍でエディフィスの危機は解決しますが、クロードたちが再集結するストーリー構成はファン向けのお祭り感が強いです。
『2』のキャラ同士の後日談的イベントや掛け合いが楽しく、彼らの成長を追体験できるのが一番の醍醐味。
見どころ・テーマ
- 『2』の仲間たちのアフターストーリー
「あのとき協力して十賢者を倒したメンバーがまた一堂に会する」というワクワク感。
各キャラのその後が気になるファンにはたまらない一作です。 - 携帯ハードらしさ
ゲームボーイカラーゆえの制約はあるが、アクションバトルやスキルシステムはスターオーシャンらしさ全開。
レア度が高いゆえに“幻の作品”とも言われます。 - 古代文明と新たな脅威
惑星エディフィスでの未知の力や遺跡が『2』とはまた違った角度でSF要素を強調し、
“シリーズはまだまだ広がりを見せるぞ”
という余韻を与えてくれます。
宇宙暦537年スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness-
作品の位置づけ
2016年発売の『スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness-』は、舞台となる惑星フェイクリードがまだ未開段階で、そこに銀河連邦やクロノスといった外宇宙の勢力が介入してくるという構図。
シリーズの中では賛否両論あったタイトルでもありますが、リアルタイムのシームレスバトルや多人数戦闘など、新しい試みがいくつか目立つ作品です。
あらすじ(ネタバレ含む)
主人公はフェイクリードの青年フィデル・カミューズ。
自分の故郷を守るために剣術や軍事的知識を活かしている最中、謎の少女リリアと出会ったことで大きな運命の渦に巻き込まれます。
リリアを狙う勢力が銀河連邦やクロノスと繋がっていることがわかり、フィデルは惑星フェイクリードだけでなく、もっと広い銀河規模の対立にも向き合わざるを得なくなるんですね。
物語が進むとリリアの正体や力の秘密が明らかになり、そこに絡む政治や軍事の陰謀、さらに外部勢力の思惑が次々と判明。
タイトルの「Integrity and Faithlessness(誠実と不実)」に象徴されるように、
誰が味方で誰が嘘をついているのか?
と疑いながら進む場面も少なくありません。
最終的にはフィデルとその仲間たちの結束が、惑星フェイクリードの未来を大きく左右します。
見どころ・テーマ
- 最大7人参加のシームレスバトル
フィールド上で敵と遭遇すると一気に戦闘開始し、仲間の人数が多い!
とにかくワチャワチャ感がすごく、
“みんなで敵を取り囲む”
のが好きな人にはたまらない。 - 惑星住民から見た銀河連邦の存在感
「外宇宙から来る人たちって何者?」
という視点が強く、未開惑星の視点が軸で描かれるのが特徴。
そこに潜む政治的駆け引きも興味深いです。 - 自分の惑星を守るための戦い
フィデルは銀河規模のスケールではなく
“あくまで自分の故郷を守りたい”
というモチベーションで動くため、大事件に巻き込まれながらも根本のテーマはわりと身近。
そこが感情移入しやすい部分でもあります。
宇宙暦583年スターオーシャン6 -THE DIVINE FORCE-
作品の位置づけ
2022年に発売された『スターオーシャン6 -THE DIVINE FORCE-』は、時系列的には5から約半世紀後の宇宙暦583年。
ダブルヒーロー制が復活し、
宇宙船の船長レイモンドと未開惑星アスターIVの王女レティシアのどちらを主人公に選べる
という往年のファンには懐かしい構成が注目を集めました。
あらすじ(ネタバレ含む)
商船イダスの船長レイモンド・ローレンスは、トラブルで惑星アスターIVに不時着。
アスターIVは銀河連邦にも属していない未開惑星で、そこに暮らすレティシア・オーシェリウス王女と出会い、彼女の国が内憂外患に悩まされていることを知ります。
最初はお互いの立場が違いすぎて話が噛み合わないものの、徐々に協力関係を築き始める二人。
さらに、レイモンドの船に搭載されていた謎のAI“DUMA”がストーリーを左右する存在となり、戦闘でもDUMAを駆使した高速移動や奇襲攻撃が特徴的。
物語後半になると
「実は銀河連邦の裏にも怪しげな勢力がいて…」
という陰謀が浮かび上がり、惑星アスターIVの自体も大きな戦火に巻き込まれそうに。
レイモンドとレティシアの視点が切り替わることで、未開惑星の文化と宇宙社会のぶつかり合いがよりリアルに描かれます。
見どころ・テーマ
- ダブルヒーロー制の復活
『2』でも採用されたシステムで、二人の主人公それぞれの目線で物語を楽しめる。
周回プレイ好きには嬉しい要素です。 - DUMAによる近未来アクション
フィールドや戦闘でDUMAを使った空中ダッシュや突撃が可能になり、シリーズ従来のARPG性がさらに強化。
高速でマップを移動する爽快感が魅力。 - 異文化交流と共存のさらなる深化
銀河連邦からすれば後進的な惑星アスターIV。
しかし実際は高度な魔術や技術を独自に発展させており、外部勢力に対して
「一方的に守られるだけじゃない」
という見せ方も面白い。
宇宙暦772年スターオーシャン3 -Till the End of Time-
作品の位置づけ
いよいよ最後が、宇宙暦772年を舞台とする『スターオーシャン3 -Till the End of Time-』。
2003年にPS2でリリースされ、
後半の超展開(仮想世界オチ)
が賛否両論を巻き起こした伝説の作品です。
ゲームシステムとしては3Dアクションバトルや戦闘中のMPが0になると戦闘不能になる仕組みなど、独自要素も多数。
あらすじ(ネタバレ含む)
主人公フェイト・ラインゴッドは、保養惑星ハイダに滞在中、謎の勢力ヴァンデーンの侵攻を受けて両親と離れ離れに。
幼なじみソフィアを守りつつ、避難先として逃げ延びたのは未開惑星など、さまざまな場所を転々とする旅になっていきます。
ところが事態はどんどん大きくなり、銀河連邦vsヴァンデーンの大規模戦争に巻き込まれ、さらには4次元世界の住人が登場。
そして終盤、
「実はフェイトたちがいるこの宇宙は、4次元世界の人間が作った“エターナルスフィア”という仮想世界だった」
という衝撃の事実が判明。
「私たちって…プログラム?!」
という壮大なメタ展開に困惑するフェイトたちですが、
「存在が人工物だろうと、私たちが考え、決意し、行動する意思は本物」
という意志を持ち、4次元世界の創造主と対決することに。
最終的に創造主の干渉を排除し、仮想世界の自由を勝ち取る結末を迎えます。
見どころ・テーマ
- 宇宙規模から次元規模へ
シリーズでもトップクラスにぶっ飛んだ設定。
“銀河連邦”という枠組みすらも、
実は4次元人が作ったシミュレーションの一部だ
という話になるわけですから、賛否の声が上がったのも無理はありません。 - 存在意義への問い
「自分たちが作られた存在かもしれない」
と知りつつ、それでも生きることを選ぶ主人公たち。
スターオーシャン最大のテーマ「運命への抗い」と「自由意志」が極端な形で描かれます。 - ドラマ性の高さ
戦闘システムや難易度面だけでなく、各キャラの背景やプライベートアクションでの掘り下げが多く、フェイトやソフィア、クリフなどの人間模様をじっくり楽しめるところはやはりスターオーシャンの醍醐味です。
系列に通じる一貫したテーマ
ここまで時系列順に作品を辿ると、スターオーシャンシリーズがただの“SF×ファンタジー混在RPG”じゃないことに気づきます。
壮大なドラマを通して、以下のようなテーマが繰り返し問いかけられているんですね。
- 未開惑星と先進文明の衝突・共存
“未開惑星保護条約”が意味するように、高度な技術を持つ者が低い技術を持つ者へ介入することの是非。
これは現実世界における先進国と発展途上国の関係にも暗喩的に通じる面があり、作品ごとのドラマに深みを与えます。 - 異文化交流と多様性
シリーズのどこでも、異なる立場や思想を持つキャラクターが共存したり対立したりします。
たとえば『2』のクロードとレナのように、
“完全に別世界の人同士”
だからこそ生まれるストーリーが魅力の中心に。 - 運命と自由意志
スターオーシャンは、
運命を変える・変えられない
というテーマを何度も扱い、『3』ではその究極形として
“実は自分たちが仮想世界の住人かもしれない”
という話にまで到達します。
それでも「自分の意思で道を選ぶ」というメッセージはシリーズ全般で一貫しているポイント。 - 科学技術と倫理
戦火の跡地から宇宙へ乗り出した『4』や、AIシステムDUMAが出てくる『6』など、
科学が発展した先にある責任
を常に描いているのがスターオーシャンらしさ。
技術革新が進めば進むほど、新たなトラブルや未開惑星への干渉リスクが増えるわけですね。
リメイク作品の盛り上がりと最新トレンド
『スターオーシャン セカンドストーリー R』の話題性
2023年11月には、『スターオーシャン2』のリメイク版である『スターオーシャン セカンドストーリー R』が発売され、多くのプレイヤーの注目を集めました。
オリジナル版から四半世紀を経てもいまだに愛される作品を、
HD-2D風のグラフィックや新システムの導入
などで大幅にブラッシュアップした形です。
- グラフィックの進化
ドット絵と3DCGをかけ合わせたHD-2Dのビジュアルは、懐かしさと新しさが絶妙に同居。
マップや戦闘画面が視覚的に一段深みを増しました。 - 遊びやすさの向上
戦闘面ではバトルテンポを改善、UI周りではメニュー操作やスキル成長システムを分かりやすく調整。
プライベートアクションやエンディング分岐も整理されており、原作ファンも新規さんもウェルカムな作り。 - ファンからの期待と高評価
発売後のSNSやレビューでも好印象な声が多く、
「やっぱりスターオーシャン2は名作だった」
「シリーズ全体をまた遊びたくなった」
という声が多数。
これをきっかけに時系列順プレイに興味を持つ人も増えています。
他作品のリメイクへの希望
ファンコミュニティでは、
「次は『スターオーシャン3』をHD-2D化してくれ!」
とか
「『ブルースフィア』も今のハードでリメイクしてほしい!」
など、妄想や要望が飛び交っています。
とりわけ『3』は衝撃的なメタ設定で賛否両論あっただけに、
「あのシナリオをリメイクでどう再構築するのか見てみたい」
という声が根強いですね。
今後のスクウェア・エニックスとトライエースの動向に注目が集まるところです。
時系列順で遊ぶか、発売順で遊ぶか?
スターオーシャンをプレイする際、よく議論になるのが
「どの順番がベスト?」
という問題。大きく分けて、
- 時系列順
- メリット:銀河連邦の起源や未開惑星保護条約の始まりを順番に体感できて、大きな物語の流れが分かりやすい。
- デメリット:発売時期の古い作品に後から戻ると操作感のギャップが大きい場合もある。
- 発売順
- メリット:システムの進化や制作側の意図を追える。最新作にいくほど洗練されたUIやグラフィックが期待できる。
- デメリット:話が前後しやすいので、スターオーシャン4の時代が一番昔だと分かりにくい…などの混乱がある。
ただし、どの作品から始めてもストーリーを追えるように作られているのがスターオーシャンシリーズの親切設計でもあります。
興味を持った作品からいきなり遊んでOK
という自由度も高いのです。
もし“どうせなら銀河連邦の誕生から4次元世界オチまで一気に味わいたい”というなら、本記事で紹介した順(4→1→2→ブルースフィア→5→6→3)でプレイしてみるのも楽しいでしょう。
ちょこっと雑談気づかない落とし穴は日常にもある
スターオーシャンでは
「知らない惑星にワープしたら、そこが大変な事件に巻き込まれていた」
とか
「未開惑星に技術を持ち込んだら大問題になった」
みたいな展開がありますが、意外と私たちの日常でも「気づかない落とし穴」は転がっているもの。
たとえば、プロパンガス料金の
“こっそり値上げ”
なんてのは現実にあるかもしれません。
ストーリー世界の危機に比べれば可愛らしいものですが、毎日の生活で地味にガス料金が上がり続けると、長期間で見れば痛い出費。
もし
「なんか最近ガス代が高いような…?」
と感じているなら、料金比較サービス“エネピ”の公式サイトあたりでサクッとシミュレーションしてみるのもアリかと。
自分の家計を守るというミクロな視点は、惑星を守るフィデルやレイモンドのマクロな奮闘とも、どこか根っこが同じような気もします。
……と言っても、スターオーシャンの世界じゃガスよりもっと大きな星間戦争が起こったりするわけですが、リアル生活の危機は何かと地味で発見しづらいものですよね。
なお、ここでは詳しく説明しませんが、見直すだけで年間数万円浮いたなんて例も普通にあります。
“気づかぬうちに結構なダメージを被ってる”あたりは、ちょっとした未開惑星が陥る深刻なトラブルに似ているのかもしれません(オーバーすぎますかね…?)。
>>ガス代が高すぎる!ガス料金の比較チェックはコチラの記事から
壮大な時空旅行を堪能するまとめ
以上、スターオーシャンシリーズを時系列順で振り返ってみました。
最後に重要ポイントをざっとまとめておきましょう。
- 『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-』(宇宙暦10年)
戦後荒廃した地球から旅立ち、未開惑星と衝突しながらも銀河連邦の萌芽を描く、シリーズ時系列上の“始まり”。 - 『スターオーシャン1 -First Departure-』(宇宙暦346年)
未開惑星ロークでの石化病問題と、地球連邦クルーとの初接触。
魔王アスモデウスやタイムスリップ要素など、ファンタジー×SFの妙が光る。 - 『スターオーシャン2 -セカンドストーリー-』(宇宙暦366年)
光の勇者と十賢者、エクスペル消滅の危機を描く大ボリュームの人気作。
2023年リメイク『セカンドストーリー R』も高評価。 - 『スターオーシャン ブルースフィア』(宇宙暦368年)
『2』の後日談として、クロードたちが新惑星エディフィスでの冒険に再集結するファン向け作品。
携帯ハードのみ展開。 - 『スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness-』(宇宙暦537年)
惑星フェイクリードの青年フィデルが銀河連邦やクロノスの陰謀と交錯。
最大7人のリアルタイムバトルが特徴的。 - 『スターオーシャン6 -THE DIVINE FORCE-』(宇宙暦583年)
商船船長レイモンドとアスターIVの王女レティシア、二人の主人公で描く壮大な物語。
DUMAによる空中ダッシュなど新アクションが注目。 - 『スターオーシャン3 -Till the End of Time-』(宇宙暦772年)
4次元人による仮想世界オチが衝撃的。
銀河連邦すら創造主の手のひらだった!?
というメタ設定でシリーズ最大級の議論を呼ぶ。
こうやって並べると、
シリーズ開始(人類の宇宙進出)から最終的には「自分たちが仮想存在かも」と気づくレベルまで、壮大なスケールが一本筋で通っている
のが確認できます。
しかもその間に登場する“異文化”は必ずしも一枚岩ではなく、主人公たちも惑星ごとに対応を変えていく。
その柔軟さがスターオーシャンらしさを支えています。
また、時系列順プレイに限らず、
「やっぱり思い入れがある作品からプレイしたい!」
でも全然OK。
どこから手をつけても一定以上の独立性があるため、そこがシリーズのとっつきやすさになっています。
最近『セカンドストーリー R』をきっかけに復帰した人や、まったくの新規で触れたい人もいるでしょうが、
好きなところから潜り、興味が湧いたら他作品に行く
というライトな感覚で楽しめるんです。
星の海へ一歩踏み出す価値まとめ
スターオーシャンシリーズは、SFとファンタジーという相反する要素をダイナミックに組み合わせることで、他にはない冒険感を味わわせてくれます。
未知の惑星に足を踏み入れるワクワク感と、そこに生きる人々との出会いによって起こる衝突や協力が、各作品ごとにしっかり“ドラマ”として仕立て上げられているのです。
さらに、最新リメイクである『スターオーシャン セカンドストーリー R』が高評価を受けたことで、シリーズ全体へ再びスポットライトが当たり、
「時系列順でリマスターやリメイク作を巡りたい」
という人が増えています。
制作側もリメイクを続けており、今後他の作品もリメイクされるかもしれません。
そうした動きが追い風になり、まだ遊んだことのない作品を手に取る人が増えるのは嬉しい流れですよね。
それと、ちょこっと話に出た“プロパンガス料金の比較”にしても、
「知らなかっただけで損していた」というケースは、スターオーシャンの未開惑星が先進文明と接触して初めて自分たちの立ち位置を知る
のにどこか似ている部分も。
私たちのリアルな暮らしでも、気づけば大きな差がついているなんてことはざらにあります。
どの惑星に住んでいても、“気づかないリスク”というのはあるものですね。
ともあれ、スターオーシャンシリーズで描かれる旅の終着点は、
「運命の鎖をどう乗り越えるか」
「自分の存在意義をどこに見いだすか」
といった、実は普遍的なテーマにも繋がっていきます。
ゲームとしての面白さはもちろんのこと、壮大なストーリーによって心を揺さぶられ、
「もっとこの世界を深く知りたい」
と思わせてくれる力があるのです。
まだプレイしていない作品があるなら、この機会にぜひ手を伸ばしてみてください。
そして既にプレイ済みの方も、今回の時系列まとめを参照しつつ再プレイすると、昔は見落としていた繋がりや伏線を再発見できるかもしれません。
何しろスターオーシャンは、仮想世界説にまで発展するほどの壮大な物語。
二度、三度と旅してもまったく退屈しないはずです。
以上、超ロング解説となりましたが、スターオーシャンシリーズを網羅的に知る上で、少しでもお役に立てれば幸いです。
ぜひ大宇宙の航路へ飛び立ち、各惑星や銀河連邦、そして自らの意思との対峙を通じて、新しい世界を感じ取ってみてください。
ゲームの中の彼らと同じく、“星の海”での発見が、きっとあなたの心にも大きな刺激を与えてくれることでしょう。
この記事は、シリーズのネタバレをがっつり含んでおりますので、これから初めてプレイする方は「覚悟の上」で閲覧いただいたという前提です。
でも多少ネタバレがあっても、実際に遊ぶと何倍も楽しめるのがスターオーシャンの妙。
気になったらぜひ、実際にゲームを手に取ってみてください。
惑星を救うヒーロー(あるいはヒロイン)は、あなたです。