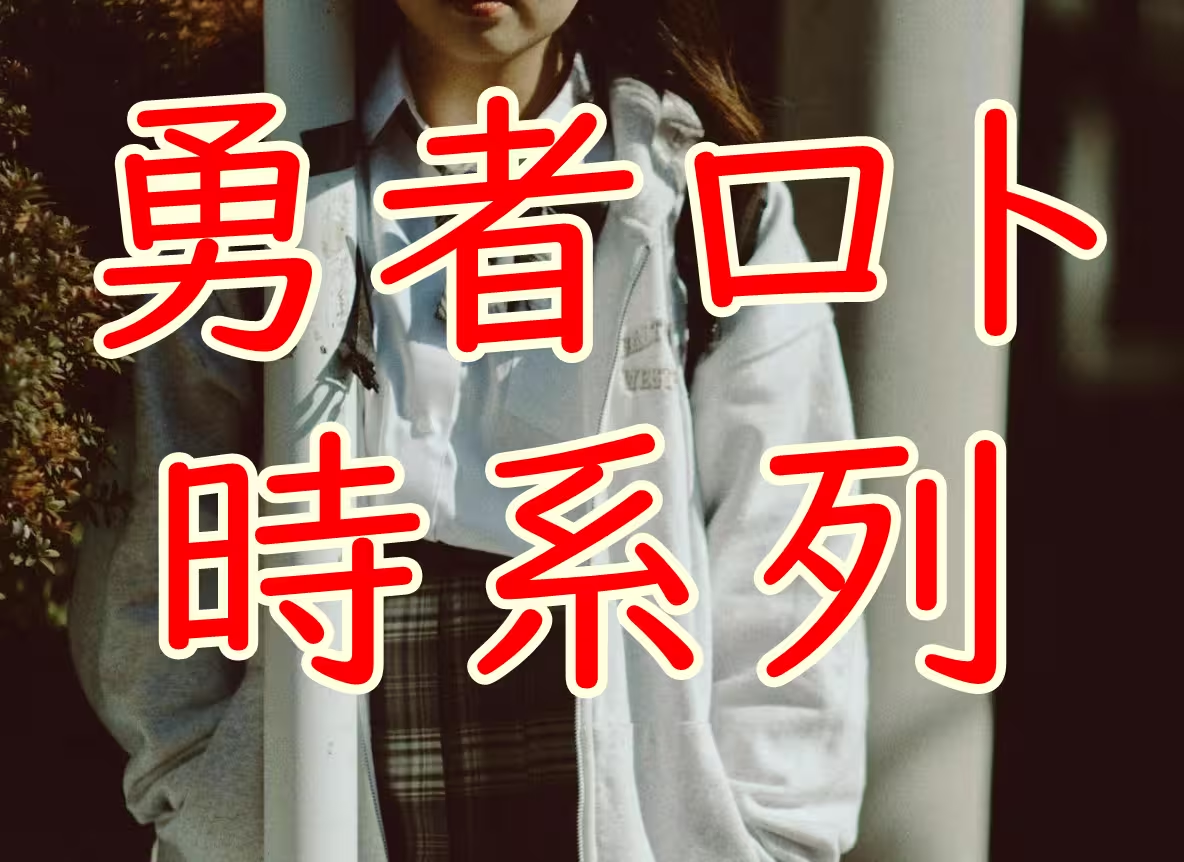ドラクエシリーズの中でも、とびきり重要な位置を占めるのが「ロトシリーズ」です。
『ドラゴンクエストXI』
『ドラゴンクエストIII』
『ドラゴンクエストI』
『ドラゴンクエストII』
という4つの作品が中核となり、それぞれが時系列でどう繋がっているのかを解説しだすと、奥深いドラマが展開されます。
本記事では、これら4作を「XI → III → I → II」の順番で完全ネタバレ上等のあらすじを紹介し、伏線やら派生作品やらを根こそぎ拾い上げていきます。
長大なロト伝説の流れを俯瞰すると、ドラクエ世界の壮大さにハマり込み、気づけばお茶請けが足りなくなるかもしれません。
結末まで言及してしまいますので、ネタバレが苦手な方はどうぞご注意あれ。
それではさっそく、この“ロトという名にまつわる時空を超えた物語”をがっつり覗いてみましょう。
スポンサーリンク
ロトシリーズとは何か
ロトシリーズといえば、かつては『ドラゴンクエストIII』『I』『II』の3作品による「ロト三部作」と呼ばれてきました。
ですが後年発売された『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』(以下、DQXI)が登場したことで、ロト伝説の真なる「始まり」がXIに位置づけられ、
実際の時系列は「XI → III → I → II」
という流れが公式に認められています。
この変更によって「IIIが最初のロトの物語」というファンの長年の認識がひっくり返され、ある意味、ドラクエ界隈でプチお祭り騒ぎが起こりました。
しかも、ロトシリーズには公式派生作品や漫画版などが複数存在します。
代表的なのは『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』という漫画作品。
ここでは、ゲーム本編では語られない「ゾーマを倒した後の世界」や「ロトの子孫が新たに王国を築いた話」などが描かれ、ファンにとっては「まるで分厚いゴーフレット」をもう一重重ねたような満腹感があります。
この記事では、ドラクエXI・III・I・IIの4作品を中心に、物語の核心部分を完全にネタバレしていきます。
内容を一通り追えば、「ロトの称号」の起源やアレフガルドの闇、勇者の血統がどうやって受け継がれてきたのかが一目瞭然に見えるはず。
そしてそこには、あまりに壮大すぎる“時空のループ”や“神話的円環”が潜んでおり、あのシンプルに見えるドラクエ世界がじつは相当込み入った歴史を秘めていることを思い知らされます。
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(最も古い時代)
ロトゼタシアと“光の子”の宿命
DQXIで描かれるのは、「ロトゼタシア」と呼ばれる世界。
今までのドラクエの舞台とは違い、“XIが最初に登場した大陸”だから、シリーズ内でどれほど他作品と関連するのか当初は謎でした。
しかし真エンディングを見るに、
「ロト」の呼称がここを発端に派生した
と判明し、長らくプレイしてきたファンは揃って驚愕したわけです。
主人公は幼い頃に故郷が魔物に襲われ、デルカダール王国の老夫婦に育てられた青年。
16歳になった時
「あなたこそ伝説の勇者の生まれ変わり」
と知らされ、世界を救う使命を帯びて旅立ちます。
途中、聖地や各地域を巡り、個性豊かな仲間たちと出会い、古の闇に挑む展開へ突き進むわけですが……
まさか後になって
“XIこそが史上最初のロト勇者になる”
なんて誰が予想したでしょうか?
発売当時のファンは混乱半分・歓喜半分、とにかく大盛り上がりでした。
中盤の挫折ウルノーガの大策略
物語が半ばを過ぎると、黒幕的存在として魔王ウルノーガが台頭し、世界の根源たる「命の大樹ユグノア」を崩壊させてしまいます。
ロトゼタシア全体が絶望の淵に叩き落され、仲間のベロニカが命を落とすなど、ドラクエ史でも屈指のダークな展開が訪れます。
それまで
「苦難にあっても笑顔で切り抜けるのがドラクエの王道」
と思っていたら、いきなりお通夜級の絶望が押し寄せるため、多くのプレイヤーが衝撃を受けました。
ベロニカの犠牲シーンはとにかく泣かされる。
火傷レベルで熱い炭水化物料理をちょっとしか頬張れない、そんな苦しさすら覚えるほどの衝撃度です。
歴史改変と真のラスボス邪神ニズゼルファ
仲間たちは一度四散するも再集結し、なんとか魔王ウルノーガを退けます。
しかしその後、主人公は「時のオーブ」というアイテムで世界が闇に落ちる前の時間軸へ戻り、歴史を変える決断をする。
「ベロニカの死ななかった世界を取り戻したい」
という、いかにも勇者らしい動機があれど、タイムトラベルの大暴挙に踏み出すのです。
結果として“改変された世界線”では、邪神ニズゼルファという真の黒幕が表舞台へ顕現。
魔王ウルノーガなど、いわば邪神の尖兵に過ぎなかったと分かります。
主人公はオリハルコンから打ち直した“真の勇者の剣”を携えて仲間と最終決戦に挑み、ニズゼルファを討ち果たすことでロトゼタシアに平和を取り戻す。
勝利後、主人公は“聖竜”から「ロトの勇者」の称号を授かり、その剣を託されるのです。
「もし私が闇に堕ちれば、その剣で討つのだ」
という、未来への示唆を残して……。
ロト誕生からのIIIへ繋がる真エンディング
DQXIのエンディング(特に真エンディング)では、賢者セニカがさらに過去へ遡って勇者ローシュを探し出し、ローシュが本来なし得なかった宿命を救済するシーンが描かれます。
ここから画面が暗転し、なんと『ドラゴンクエストIII』のオープニングを想起させる演出が流れるのです。
つまり、XIがあくまで“ロトシリーズの最初” に位置し、その伝説がはるか遠い時空を超えてIIIへ繋がることが公式に示されたわけです。
発売順で言えば全然後の作品が、一気に物語の最前史を担うなんて、ドラクエのなかでも超ド級の再構成でした。
このXI→IIIの流れを強烈に押し出したのがDQXIの真エンディング最大の醍醐味であり、ファンのテンションを実に爆上げした要因でもあります。
ドラゴンクエストIII そして伝説へ…(第二の時代)
世界を覆う闇とバラモス→ゾーマへの展開
DQIIIの主人公は「アリアハン国の若き勇者」。
世界各地を旅し、魔王バラモスを倒すことが当初の目標ですが、その実バラモスは大魔王ゾーマの単なる手下に過ぎません。
ゾーマが現れて大地を裂くと、その裂け目の先には地下世界アレフガルドが広がっており、そこでシリーズを遊んだファンにとってはお馴染みのラダトームやメルキドといった地名がバッチリ出てきます。
DQIをやった人からすれば
「あ、このアレフガルドってIの舞台だった場所じゃん?」
となり、発売当時はそりゃもう興奮の嵐でした。
そもそも
「IIIの世界とIの世界が繋がってるってどういうこと?」
と、初見プレイヤーの頭はゆでスパゲッティのようにクニャクニャになったはずです。
アレフガルドの闇と光の玉
大魔王ゾーマが闇の衣を纏っているため、“光の玉”が無いとダメージを与えられない設定。
光の玉といえばDQIでも重要なアイテムでしたが、ここで
「実はIIIの勇者(主人公)がゾーマ討伐の際に活用したものが、時代を超えてラダトームに伝わっていた」
という形で伏線が回収されます。
アレフガルドの住民は
「闇が晴れる日なんて来るわけがない」
とすっかり投げやり状態。
それを見て「自分は本当にロトの子孫なのかな?」と不安になるプレイヤーも多かったでしょう。
が、最終決戦でゾーマを撃破して闇を祓った瞬間、王が「おまえこそロト!」と称号を与えてくれるという展開。
ここで“勇者ロト”が誕生し、「そして伝説へ…」という名文句が出てくるわけです。
こうしてDQIIIは、それまで誰も知らなかったロトの起源(発売当時はIIIこそ最初のロトだと思われていた)を見事に描き、Iへと繋ぐ感動的なフィナーレを迎えます。
いまやXIが先に入るので、
「ロトってXI主人公から始まったんでしょ?」
と思う人も多いですが、当時はIIIのラストこそがロトシリーズの起点でした。
時空を超える説XIとの繋がり
DQXI発売により
XI真エンディング
⇒IIIオープニングへ直結
という公式演出がなされたため、IIIの主人公がロトを襲名した背景にはXI主人公やローシュ、セニカの時間遡行が深く関わっていると匂わされます。
ここには二つの大きなファン議論があるようです。
1つ目は「XIの主人公が初めてロトを名乗ったから、すでにそれが伝説としてIII世界に届いていた」という説。
2つ目は「セニカが作り直した歴史そのものがIIIへと繋がる分岐世界であり、XIとIIIはパラレルルート」という説。
公式はあえて明確には語らないため、プレイヤー間で“シュレディンガーのロト”状態が続いています。
ただいずれにせよ、ドラクエIIIこそがロト称号をアレフガルドに浸透させ、後世のI・IIにつなぐ超重要作品である事実は揺るぎません。
その渦中でXIの存在がさらに深みをもたらした、というまとめ方になるでしょう。
ドラゴンクエストI(第三の時代)
竜王に奪われた光の玉とロトの子孫
DQIは1986年発売で、シリーズの起点となった歴史的作品です。
しかしストーリー上は「IIIから数百年後」のアレフガルドで、「ロトの血を引く勇者」が再び現れて世界を救う役目を担う物語。
ラダトームの王に
「竜王を倒して光の玉を取り戻してくれ」
と頼まれ、あの狭いアレフガルドのフィールドをちまちま探索するシステムです。
竜王は「闇に堕ちたドラゴン族の王」といった扱いで、DQXIの設定から後付けすると
「聖竜が闇落ちした血筋の一端かもしれない」
という解釈が生まれます。
事実、「もし私が闇に落ちたら、この剣で斬ってほしい」と聖竜がXIで語っていたのが、DQIの竜王撃破で果たされた…
などという長大な因果が考えられるわけです。
ここがスゴイ。
ローラ姫救出とロト装備
DQIの主人公は、とにかくソロで黙々とレベル上げし、町人からの噂話を集めつつ探索し、“ロトの剣・ロトの鎧”を見つけ出して竜王城へ向かいます。
王子・王女の仲間がいたIIやIIIと比べると地味めですが、その分「ひとり旅」のヒロイズムが濃密。
物語中盤では竜王に攫われたローラ姫を救い出すイベントがあり、
「あなたこそ真の勇者ロトの血を引く者」
と姫が確信する演出が入ります。
ロト装備を全部そろえると、まさに“伝説を継ぐ者”として力が漲る感じがあって、当時のプレイヤーを虜にしました。
竜王との戦いとラストシーン
物語クライマックスで、竜王が「世界の半分をおまえにやろう」と誘惑してくるのはシリーズ屈指の名場面。
一度受け入れてみると即座にバッドエンド扱いされるという面白い仕掛けまである。
そこで拒否して戦闘に突入し、巨大なドラゴン形態へ変化した竜王を倒すと世界から闇が消えて光の玉が戻ってくる。
王から国を譲られるも主人公は辞退し、ローラ姫を連れて「ほかの場所に自分たちの国を築くんだ」と海へ船出して終幕。
このラストシーンこそ、DQIIの三王国(ローレシア・サマルトリア・ムーンブルク)の起源になっている要素です。
XIとの伏線約束された竜との因縁
DQIの竜王撃破が、XIで語られた「闇落ちした竜を倒す役目」を果たしたのだ…
という繋がりがファンの間で支持されています。
もちろんDQI発売時にそんな話は微塵もありませんでしたが、XIで後付けな設定を提示し、
「じつはこういう深い因果があったんだよ」
という神話的なストーリーテリングに仕立て直しているのが醍醐味。
こんな風に、30年以上前の作品が新作で再定義されるわけです。
おそらく当時の開発スタッフもこんなループ展開にするなんて考えていなかったでしょうが、結果的にロトシリーズが幾層にも重なる複雑な歴史を手にしたのだから、ファンとしては面白い限り。
ドラゴンクエストII 悪霊の神々(第四の時代・最終章)
ロトの血筋が3系統に分岐
DQIのラストで主人公とローラ姫が旅立ち、彼らの子孫が100年後にそれぞれ王国を築いた…
という設定がDQIIのベースです。
すなわちローレシア、サマルトリア、ムーンブルクの三国はみなロトの血を引く王家。
そのためDQIIの主人公一行は、いわばいとこ同士という立ち位置で、これは歴代ドラクエでも珍しい形のパーティです。
スタート地点のローレシアは主人公が王子としてすでに成人(?)しており、サマルトリア王子を探し出して仲間に加え、さらに魔物の呪いで犬の姿に変えられてしまったムーンブルク王女を元に戻す。
ここから3人パーティでハーゴン討伐へ挑む流れがDQIIの醍醐味となっています。
大神官ハーゴンと破壊神シドー
物語冒頭でムーンブルク城がハーゴン軍に襲撃されるインパクトはなかなか凄まじい。
「ロトの血を引く王女の国がいきなり滅ぼされた」
と開幕ショッキング。
敵役のハーゴンは「破壊神シドーをこの世に降ろそう」と企む邪教の大神官です。
ゲーム的には、ローレシアからスタートして比較的広大な世界を巡ることになり、当時のファミコンRPGとしては抜群に探索範囲が広い。
その分、ロンダルキアへの洞窟など鬼畜難易度のダンジョンが用意されており、多くのプレイヤーがブリザードのザラキに泣かされました。
終盤、ハーゴンを倒したかと思いきや、彼が命と引き換えに破壊神シドーを召喚し、プレイヤーに連戦を強いる流れは緊張度マックス。
シドーは凶悪な攻撃力・呪文も持ち、シリーズ屈指の強敵として有名です。
無事倒せば世界は救われ、ハーゴンの邪教は崩壊するというわけ。
エンディングロト伝説の完結
DQIIのラストは、ローレシア王が戻ってきた主人公を称え、サマルトリア王子・ムーンブルク王女も自国へ帰還して三王国が平和を享受するという、ハッピーエンド。
その最後に表示される「そして、伝説が終わる…」の一言が重みたっぷり。
この「ロト伝説の完結」感は、III→I→IIという順序なら確かに物語がきれいに締まります。
そしていまやXIがそこへ先行するため、より一層「長い長いロトの血統サーガ」が結末を迎えた…
という壮大な印象が強まりました。
DQIIにおける“ロトの最後の闘い”は、ある意味シリーズの根幹をまとめ切る大仕事を果たしていると言えます。
公式派生作品や関連設定
漫画『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』
ロトシリーズファンなら一度は耳にしたことがあるであろう漫画作品。
ゾーマを倒した直後の世界からスタートし、勇者ロト(作中ではアレル)と仲間たちが地上世界に帰還し、それぞれローラン・カーメンという国を興し……
というストーリーが描かれます。
この漫画内では、ロトの直系子孫が次々と登場し、邪悪な異魔神や魔人王ジャガンなど新たな敵との戦いが展開されます。
細部の設定(魔法の名称など)はゲーム本編と違う点もあり、パラレル要素を含むため完全正史には組み込まれていません。
しかし、「ロトの血統がどう発展してDQIやIIへ繋がるか」を補完するような部分があり、多くのファンは“公式に近い外伝”として好意的に受け止めています。
小説・公式ガイド・設定資料
他にも「小説版 ドラゴンクエストIII」や「精霊ルビス伝説」などで、ルビスという存在がアレフガルド創世に関わっていたことや、勇者が転生を繰り返す設定などが言及されています。
ゲーム本編で曖昧にされている部分が詳細に描かれる反面、公式ゲームと食い違う描写もあるため、どこまで正史と見なすかは人それぞれ。
ただ、これらの小説を読めば「ルビスが世界を見守っている理由」や「XIとIIIの勇者の魂が同一なのでは?」といった考察が捗ること間違いありません。
ビルダーズやヒーローズ系のパラレルワールド
- ドラゴンクエストビルダーズ:もしDQI主人公が竜王の誘いに乗って“世界の半分”を受け取ってしまったら……というIF展開を描いたブロックメイクRPG。荒廃したアレフガルドを“ビルダー”が再建していくストーリーで、ロトシリーズの舞台設定が隅々まで活かされています。正史ではないものの、この世界線での主人公がどのように竜王やロト伝説と向き合うかは非常に興味深い。
- ドラゴンクエストヒーローズ:シリーズの登場人物がクロスオーバーするアクションRPGですが、ロト装備が最強装備として用意されるなど、やはりロトの名は別格の扱いを受けています。特に時空を越えたキャラ集合という設定は、実質パラレルワールドのような位置づけと考えられます。
ロトシリーズを貫くテーマと魅力
時空を超える円環構造
XIが最古の時代、そこからIII、そしてI、最後にIIへと続くという構図は、最終的にロトの称号が誕生し、伝説が確立し、血統が繁栄し、そして完結するまでを何重にも結びつけました。
最初はIIIが始まりだとずっと思われていたのが、XIによってひっくり返されたため、これまでの物語が新たな光で再評価されることに。
そういった
後付け拡張
は賛否を呼ぶものの、少なくとも壮大な円環神話としての完成度は高くなり、ファンの楽しみが倍増しました。
たとえばXIを初プレイし
「ロトとは何ぞや?」
と思った新規ユーザーがIII→I→IIと遊べば、
「なんだ、全部繋がっていたのか!」
という気づきを得てめちゃくちゃ感動しそうです。
血統&転生
ロトシリーズを語るうえで、血統と転生の概念は外せません。
III主人公がロトとなり、その血がI→IIへ引き継がれ、さらにXIの主人公や勇者ローシュと結びついている。
実際には同じ血の話なのか、あるいは魂の循環なのか曖昧ですが、ファンの間では
「みんな同じ魂が時代ごとに現れる転生勇者説」
が有力視されています。
転生云々と聞くと“ファンタジー感マシマシ”ですが、ドラクエというブランドだから受け入れやすい。
いろいろ考え始めると頭がパッと花開いた花畑のように盛り上がるところがドラクエの魔力です。
世界構造アレフガルドと地上世界の分離
IIIで登場した上の世界と下の世界(アレフガルド)
という設定が、IとIIの閉鎖的なワールドを説明するうえで重要な役割を担っています。
アレフガルドは大魔王ゾーマが闇に包んでいた地下世界で、III主人公が救った後も地上との行き来はそこまで頻繁ではないらしく、IやIIの時代には独自の進化を遂げています。
DQXIでの舞台・ロトゼタシアはまた別の世界とも言える構造。
マップの成り立ちや大陸の位置関係など、どこまで繋がりがあるのかは公式も詳細を明かしていません。
ファンがいろいろ推測できる余地を残してくれている点が、シリーズを何度でも味わい尽くせる要因とも言えましょう。
ロト装備という象徴
ロトの剣・ロトの鎧・ロトの盾・ロトの印は、シリーズを象徴する伝説装備。
IIIで主人公が扱った“王者の剣・光の鎧・勇者の盾・聖なる守り”が後世で名称を変えDQI・IIへ受け継がれる構成です。
XIでは「勇者の剣・真」が登場し、最後に聖竜が主人公へ「ロトの勇者」の称号とともに剣を託すシーンがあるわけで、ここでまた「ここからすべてが始まった」というロマンが加速。
もしXIの物語を知らずにIIIやIをプレイしていた人は、XIを後からやって
「ああ、俺たちが何十年も使ってきたロト装備の原点はココか!」
と、草餅をもう2個ぐらい食べたくなる感じの満足感を得られるというわけです。
複数時間軸と世界線の可能性
DQXIは
「一度世界が滅びてしまった後、主人公が過去へ戻って歴史をやり直す」
という大胆展開を見せ、さらに賢者セニカが別の過去へ飛ぶなど、タイムトラベルしまくりのシナリオになっています。
これによって
「改変前と改変後、両方の時間軸が存在するんじゃない?」
というパラレルワールド説が活発化。
ですが堀井雄二氏は
「シリーズは最終的に一つに収束するんですよ」
と柔らかくほのめかす程度で明確な答えを語らず。
その結果、ファンの考察バトルがエンドレスになり、むしろ盛り上がる要素となっています。
混沌こそがシリーズの魅力、という実にドラクエらしい構図です。
今後の展開
ドラゴンクエストXIIとロト
既に制作発表があった『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎(仮題)』が、ロトシリーズにどう関わるかは一切未知です。
XIにおいてロトの原点が描かれた以上、XIIで再びロトがクローズアップされるのか、それともまったく新たな世界・新要素で攻めるのか。
ドラクエ本編は作品ごとに世界が独立しているケースが多いため、ロトシリーズを越えて完全新規という可能性は十分高い。
が、「XIで始まった再構築を継続してほしい」「もうちょいロト絡みの謎を回収してほしい」と願うファンも多いことでしょう。
スクエニさんの采配がどちらに転ぶか、楽しみに待ちたいところです。
ロトサーガの本質と魅力まとめ
ここまで、「XI → III → I → II」という流れで物語を追ってきました。
実際にゲームをプレイする際は、発売順にあたる
「I→II→III→XI」
「XI→III→I→II」
の順、あるいは
「III→I→II→XI」
の順で楽しんでもOK。
どの順番でやるにしても、“ロト”というキーワードで全部が一本の壮大な川のようにつながっている事実を強く感じられます。
- 『ドラゴンクエストXI』:ロトゼタシアでの魔王ウルノーガ撃破、邪神ニズゼルファ討伐、そして主人公が“初代ロトの勇者”となり聖竜から剣を託される物語。
- 『ドラゴンクエストIII』:アリアハンの勇者が魔王バラモス→大魔王ゾーマを倒し、アレフガルドを救って “ロト” の称号を得る。伝説はここで歴史上初めて(発売順としては)明確化された。
- 『ドラゴンクエストI』:竜王に奪われた光の玉を取り戻すべく、ロトの子孫がラダトームから旅立ち、ローラ姫を救出して世界を再び光に導く。
- 『ドラゴンクエストII』:ローレシア・サマルトリア・ムーンブルク三国の王族(全員ロトの血を引く)が力を合わせ、大大神官ハーゴン→破壊神シドーを下し、ロトの長い物語に終止符を打つ。
さらに、周辺作品の漫画や小説が、IIIとIの合間を埋めたり、ロトの家系譜がいくつも派生したり、ビルダーズなどのIF世界線が用意されたりして、もう菓子折り3箱分くらいのボリューム感をもった“ロト神話”が出来上がっています。
ドラクエというシリーズが長きにわたり愛される背景には「懐の深い世界観」があると言われますが、ロトシリーズはまさしくその真骨頂。
後付け要素を飴細工のように絡ませつつ、ファンが考察し続けられる拡張性を保っています。
ここまで読んで「もう全部頭に入ったよ!」という方は、ぜひ改めてロトシリーズのプレイを検討してみてはいかがでしょう。
プレイ済の方なら「XIからやり直そうかな」と思うかもしれませんし、未プレイの方でも「じゃあ発売順にI→II→III→XIでやってみよう」と興味を抱くかもしれません。
いずれにせよ、ロトの物語がただの“勇者伝説”に留まらない深みを持っているのを、ご自身の目で確かめていただきたいところです。
最後に、ロトシリーズの何がすごいかと問われれば、“シリーズをまたぐ壮大な時間の流れ”が根っこにあるからこそ、数十年経っても新たな解釈が加わり、ファンが未来永劫語り尽くせるネタを提供している点です。
XIでロトが始まり、IIIで伝説が確立し、I→IIで血が繁栄・完結するという大河ドラマ。
この円環のストーリーを追うほどに、“ロト”という言葉がただの固有名詞ではなく、プレイヤーの心を揺さぶる象徴へと昇華しているのを感じるはず。
今後、I・IIのリメイク版、あるいはドラクエXIIなどで、さらにロトの神秘が明かされるのかどうか。
一度その可能性を想像しだすと、まるで本場のちゃんぽんを啜っているうちに具材が永遠に出てくるかのごとくワクワクが止まらなくなる。
ドラクエという歴史の奥深さ、そしてロトシリーズという核は、今なお新たな光を放ち続けています。